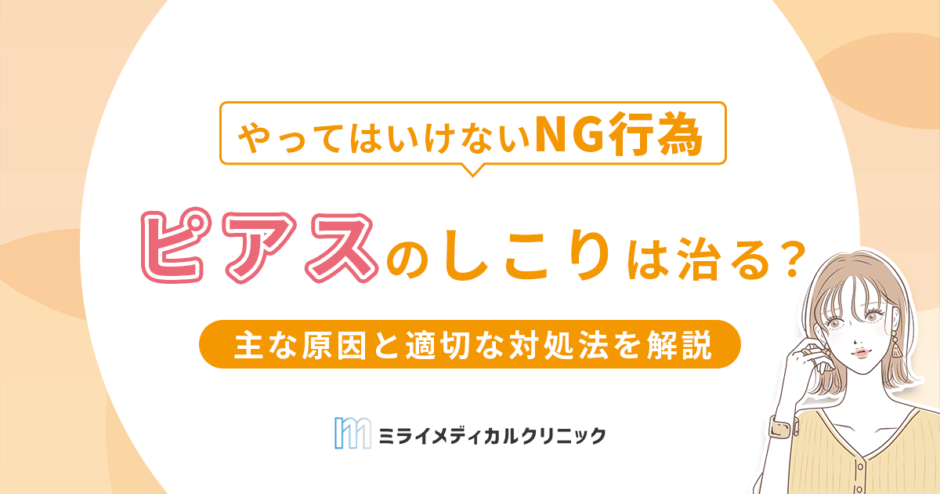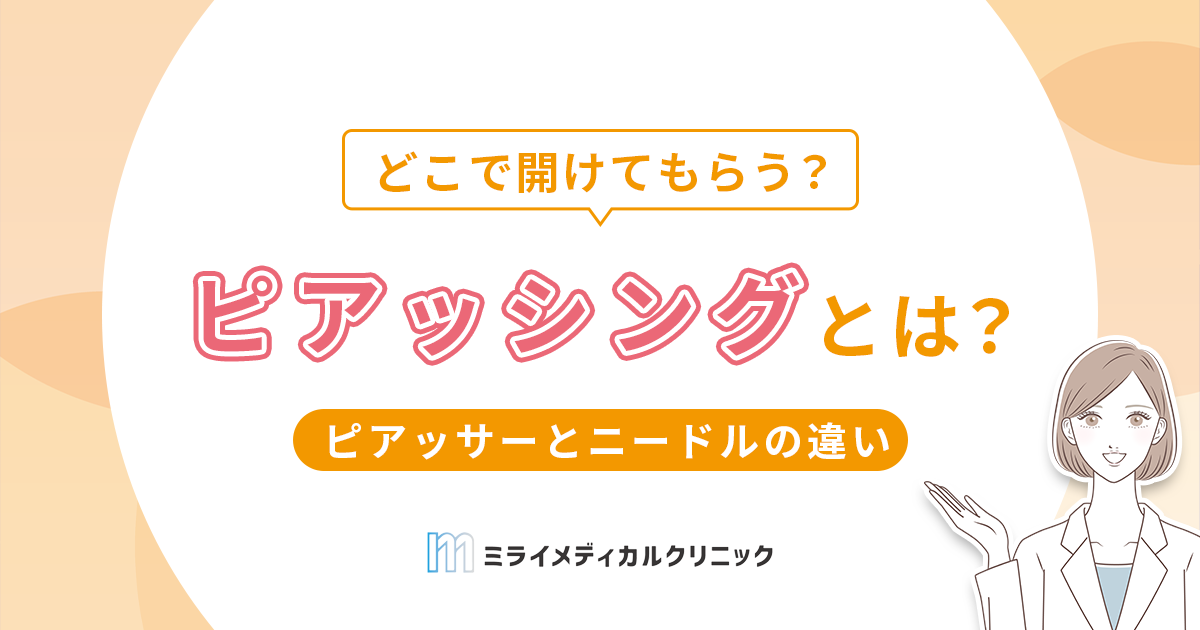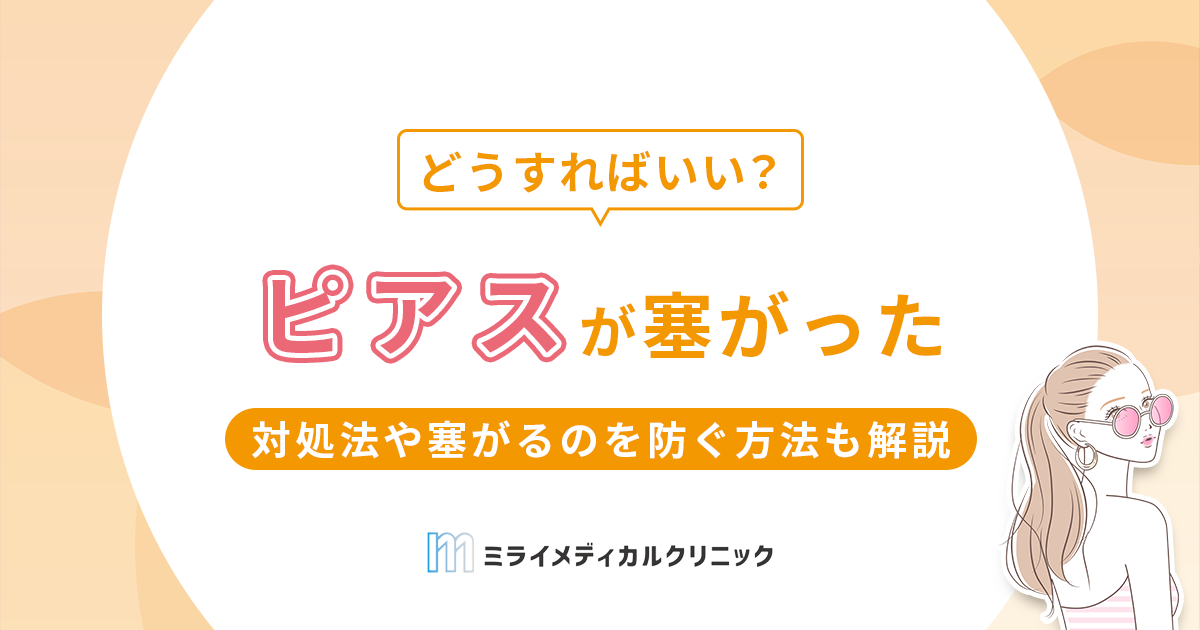ピアスホールにできるしこりは、その原因や症状によって対処法が異なります。軽度のものであれば自然に治まることもありますが、適切なケアをしないまま放置すると、炎症が悪化したり、感染症のリスクが高まったりする可能性もあります。
この記事では、ピアスにしこりができる主な原因や、しこりができたときの正しい対処法、そして避けるべきNG行為について詳しく解説します。ピアスを楽しむためにも、トラブルに適切に対応するための知識を身につけましょう。
目次
ピアスにしこりができるのはなぜ?主な原因を解説
ピアスの穴周辺にしこりができて不安になる方は少なくありません。耳たぶ、耳の軟骨、耳の裏など、ピアスを開けた場所にできるしこりは一体何が原因なのでしょうか。ここでは、ピアスのしこりの主な原因を3つ解説します。
しこりの原因1|粉瘤
ピアスホールのしこりの原因の一つに、粉瘤が挙げられます。粉瘤とは、皮膚の下に袋状のものができ、その中に老廃物や垢が溜まってしこりになるものです。
ピアスの穴だけでなく、ピアスを開けていない部分にもできることがあります。耳たぶのしこりだけでなく、耳たぶの中にもできる場合があり、ピアスホールが塞がった後にもしこりが残ることがあります。
しこりの原因2|肉芽腫
ピアスホールのしこりの原因として、肉芽腫も考えられます。肉芽腫は、ピアスを開けたことによる炎症反応で、毛細血管が増殖してできる柔らかいしこりです。
ファーストピアスを着けているときだけでなく、ピアスが安定した後にもできることがあります。ピアスホールの黒いしこりや、ピアスホールが痛くないしこりの場合でも、肉芽腫の可能性があります。
しこりの原因3|ケロイド
ピアスの傷跡が赤く盛り上がり、しこりのように硬くなるケロイドも、ピアスのしこりの原因の一つです。ケロイドは、ピアスを開けた後の傷の治癒過程で、皮膚が過剰に反応してできるものです。
耳たぶのピアス跡にしこりができたり、ピアスを塞いだ後もしこりが残ったりすることがあります。ピアスのかゆいしこりや、ピアスが通らないしこりの場合、ケロイドの可能性も考慮し、皮膚科を受診するのが良いでしょう。
ピアスにしこりができたときの対処法3選
ピアスの穴周辺にしこりができてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。ここでは、ピアスにしこりができたときの対処法を3つ紹介します。
対処法1|ホットソーク(温塩水でのケア)
ホットソークは、軽度の炎症や細菌感染が原因でできたしこりに有効なケア方法です。温かい生理食塩水にピアスホールを浸すことで、血行を促進し、老廃物の排出を促します。また、塩には殺菌効果も期待できます。
- 清潔な容器に、人肌程度の温かいお湯を用意します。
- お湯に対して0.9%程度の塩分濃度になるように、精製塩を溶かします。
(例:コップ1杯(約200ml)のお湯に小さじ1/4程度の塩) - しこりができた部分が十分に浸るように、5~10分程度浸します。難しい場合は、清潔なコットンやガーゼに温塩水を浸し、しこりの部分に当ててください。
- 終わったら、清潔なタオルやティッシュで優しく水分を拭き取ります。
- これを1日に数回、症状が落ち着くまで繰り返します。
- お湯は必ず人肌程度の温度にしてください。
- 塩分濃度が高すぎると刺激になるため、適切な濃度を守ってください。
- ホットソーク後は、しっかりと水分を拭き取り、乾燥させてください。
対処法2|ピアスの素材やデザインを見直す
ピアスの素材が合わなかったり、デザインがピアスホールに負担をかけていたりすることも、しこりの原因となることがあります。特に、金属アレルギーを起こしやすい素材(ニッケル、コバルトなど)のピアスは、アレルギー反応によって炎症が起き、しこりができることがあるため注意しましょう。
| ピアスの素材 |
|---|
| サージカルステンレス、チタン、ゴールド、シルバーなど、アレルギーを起こしにくい素材のピアスを選ぶようにしましょう。特に、初めてピアスを開けたばかりの方や、金属アレルギーの心配がある方は、これらの素材を選ぶことをおすすめします。 |
| ピアスのデザイン |
|---|
| キャッチが皮膚に食い込みやすいデザインや、重すぎるピアスは、ピアスホールに負担をかけ、炎症やしこりの原因になることがあります。シンプルなデザインで、ホールに負担のかからない軽量なピアスを選ぶようにしましょう。 |
| ピアスの清潔さ |
|---|
| ピアス本体やキャッチが汚れていると、細菌感染のリスクが高まります。定期的に洗浄し、清潔な状態を保つように心がけてください。 |
これらの対処法を試しても症状が改善しない場合や、しこりが大きくなる、痛みやかゆみが強いなどの症状がある場合は、自己判断せずに皮膚科を受診してください。しこりの原因によっては、医療機関での適切な治療が必要となる場合があります。
対処法3|病院(皮膚科や形成外科)を受診する
ご自身でのケアを試みても、しこりの状態が改善しない場合や、むしろ悪化しているように感じる場合は、迷わず医療機関を受診してください。
特に、しこりが急に大きくなった、強い痛みやかゆみを伴う、膿が出ているなどの症状がある場合は、皮膚科や形成外科を受診することで、原因に合わせた適切な治療法を提案してもらえます。自己判断で放置したり、市販薬で対処したりするのではなく、専門家の指示に従うようにしてください。
ピアスのしこりができた時にやってはいけない3つのNG行為
ピアスの穴周辺にしこりができてしまった際、焦って不適切な対処をしてしまうと、症状を悪化させたり、治癒を遅らせたりする可能性があります。ここでは、しこりができた時に絶対に避けるべき3つのNG行為を紹介します。
NG行為1|しこりの上からピアスを開け直す
新しいピアスホールを作ろうとして、しこりの上からさらにピアスを開け直すのは絶対にやめましょう。これは、しこりの内部に新たな傷を作り、炎症や感染を広げる原因となります。また、しこりの種類によっては、無理にピアスを通すことで悪化する可能性もあります。ピアスを開け直す場合は、必ずしこりが完全に治ってから、清潔な環境で行うようにしてください。
NG行為2|しこりを無理に潰したり頻繁に触る
気になるしこりを指で頻繁に触ったり、無理に潰そうとしたりする行為は、炎症を悪化させるだけでなく、細菌感染を引き起こす可能性を高めます。また、潰そうとすることで周囲の皮膚を傷つけ、さらに状態を悪化させることもあります。
しこりは、できるだけ触らないようにし、清潔な状態を保つように心がけてください。自然に治癒を促すためには、安静にすることが大切です。
NG行為3|消毒や洗浄のしすぎや刺激の強いケア
しこりができた部分を清潔に保つことは重要ですが、過度な消毒や洗浄は、皮膚に必要な油分を奪い、乾燥や刺激を引き起こすことがあります。特に、アルコール濃度の高い消毒液を頻繁に使用すると、皮膚への刺激が強く、炎症を悪化させる可能性があります。
また、刺激の強い軟膏やクリームを自己判断で使用することも避けるべきです。ケアを行う場合は、低刺激性の洗浄剤や、医師の指示に従った適切な外用薬を使用するようにしましょう。ホットソークなどの優しいケアを基本とし、過度な刺激は避けることが大切です。
ピアスにしこりができたら医療機関を受診しよう
ピアスホール周辺にしこりができる原因は主に「粉瘤」「肉芽腫」「ケロイド」の3つが考えられます。これらは見た目や感触が似ていることもあり、素人判断では区別が難しい場合があります。
しこりができた際の対処法としては、温塩水でのホットソークによるケア、アレルギーを起こしにくい素材への変更、そして医療機関の受診が挙げられます。特に注意すべきは、しこり上からの再ピアッシング、無理な圧出、過度な消毒などのNG行為です。これらは症状を悪化させるリスクがあります。
ピアスのしこりは放置すると感染症のリスクが高まったり、見た目が悪化したりする可能性があります。軽度のものであればホットソークなどの自己ケアで改善することもありますが、症状が続く場合や悪化する場合は、早めに皮膚科や形成外科を受診しましょう。