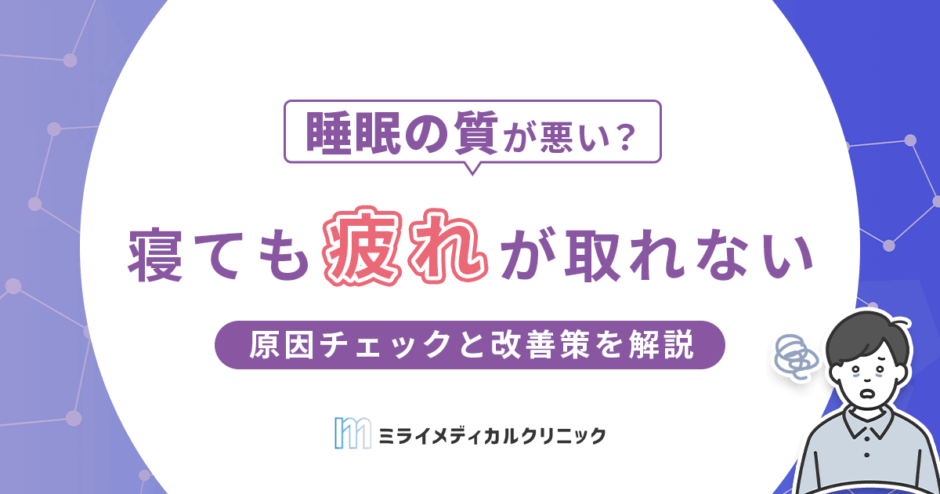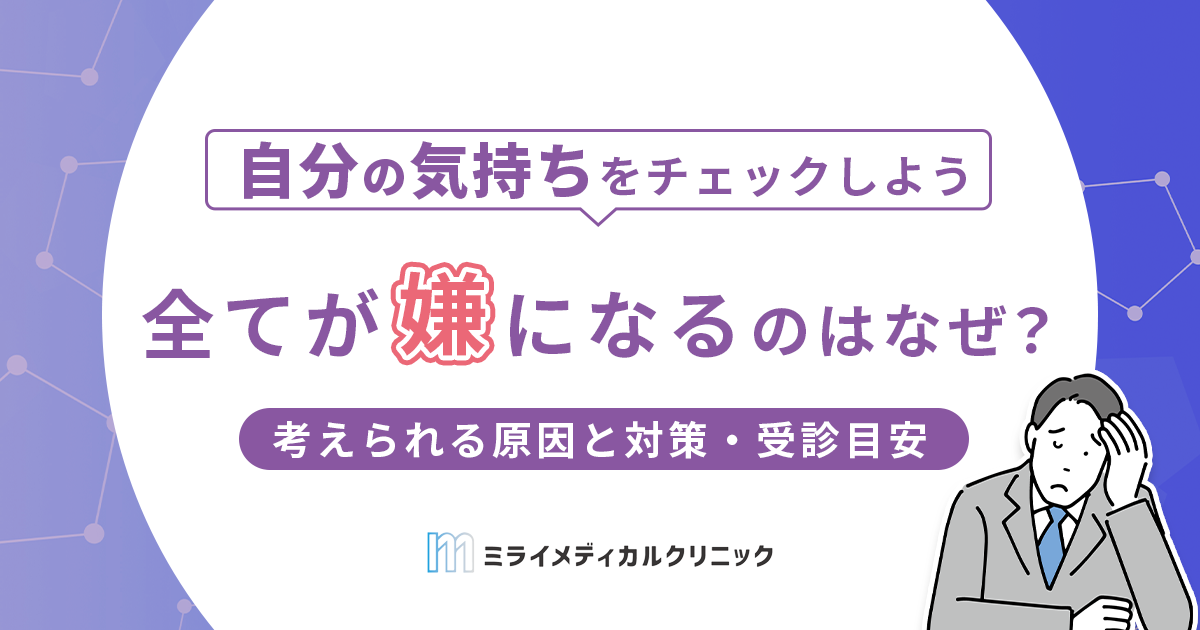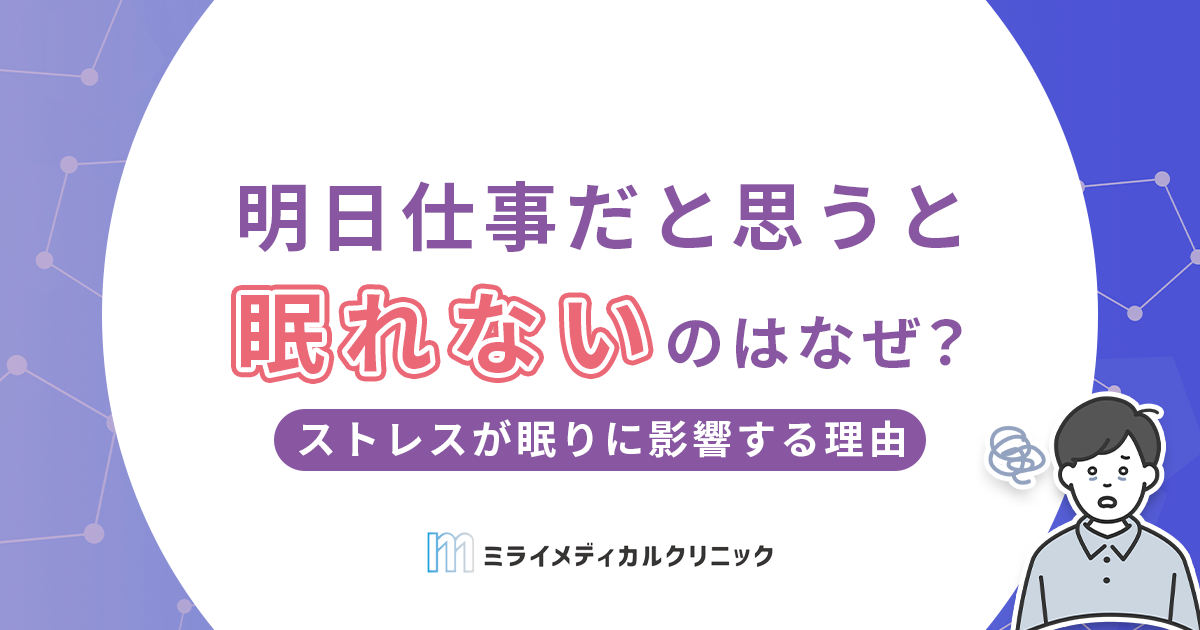「しっかり寝たはずなのに、朝からだるい」「週末にたくさん寝ても疲れが抜けない」
こうした悩みを抱える人は少なくありません。原因がわからないまま疲れが続くと、体力の問題や気の持ちようだと考えてしまう人もいます。
しかし、実際には睡眠の質の低下やストレスの蓄積、体調やホルモンバランスの乱れが関係しているケースが多いです。何も対処しなければ、集中力や意欲が低下し、日常生活に支障をきたすおそれがあります。
この記事では、疲れが取れない原因をセルフチェックで見極める方法に加え、タイプごとの特徴や対処法、医療機関を受診すべき目安も解説します。慢性的な疲労感に悩んでいる方は、改善のきっかけとして参考にしてみてください。
目次
寝ても疲れが取れないのは珍しくない
疲れが取れないと感じる人は少なくありません。2024年に行われた民間の意識調査では、全体の約60%が「疲れが取れない」と答え、63%が「日中に眠気を感じることがある」と回答しています。
こうした状態は、睡眠時間の長さだけが原因とは限りません。実際には、睡眠の質の低下やストレスの蓄積、生活リズムの乱れなどが重なり、疲労がうまく回復できないケースもあります。
気のせいや年齢の影響と決めつけてしまうと、体が発するサインを見落としやすくなります。疲れを感じる日が続いているなら、自分の状態を見つめ直すことが改善への第一歩です。
参考:クロス・マーケティング「疲労と睡眠に関する調査(2024年)」
疲れが取れない原因をセルフチェック
疲労感が続いているときは、自分の状態を客観的に見直す姿勢が大切です。原因はひとつに絞れない場合も多く、睡眠や心の状態、体調の乱れなどが複雑に関係しているケースも見受けられます。
以下のチェック項目を確認しながら、どのような傾向が自分に当てはまるかを把握してみてください。
該当項目が多い人は、心身のバランスが乱れている可能性があります。
疲れが取れない人に多い3つのタイプ

疲れが取れない人には、いくつかの共通した傾向が見られます。ここでは、タイプごとの特徴を見ていきながら、自分に当てはまりそうなパターンを探ってみてください。
タイプ1|睡眠の質が低い人
深い眠りが取れていないと、朝の目覚めがすっきりせず、疲れが残りやすくなります。睡眠時間は足りていても、夜中に何度も目が覚める場合は、睡眠の質が十分に確保されていない状態です。
生活リズムの乱れやスマホの使用、寝室の環境などが影響していることが考えられます。
タイプ2|ストレスや脳疲労が蓄積しやすい人
脳がしっかり休息できていないと、眠っていても疲れが抜けにくくなります。強いストレスが続くと、交感神経が優位な状態が続き、心身が緊張しやすいためです。
心身の緊張が続けば、不安感や気分の落ち込みといった症状が現れるおそれがあります。
タイプ3|体調やホルモンの乱れが出やすい人
食欲不振や冷え、生理不順などの不調がある人は、栄養不足やホルモンの乱れによって疲れが抜けにくくなっている可能性があります。体内のバランスが崩れると、だるさや慢性的な疲労感が続きやすくなるでしょう。
特に、鉄分やビタミンの不足に加えて、甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)、性ホルモン(エストロゲンなど)の分泌異常があると、代謝機能が低下し、全身のエネルギー産生が滞ってしまいます。
今日からできる疲労回復のセルフケア
疲れをため込まないためには、日々の生活の中で小さな工夫を積み重ねることが大切です。
ここでは、睡眠・ストレス・体調の3つの視点から、今日から取り入れられるセルフケアを紹介します。
ぐっすり眠るための夜の過ごし方
睡眠時間は確保できているのに、起きたときに疲れが抜けていないと感じる場合は、睡眠の質に問題があるケースが多いです。質の高い睡眠には、入眠前の過ごし方や環境づくりが大きく影響します。
- 寝る90分前からスマホやPCを見ない
- 就寝前は湯船に10〜15分浸かってリラックスする
- 寝室は暗く・静かに・快適な温度(20〜25℃)に保つ
- 朝起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びる
ストレスをリセットするための意識的な休息
強いストレスや脳の使いすぎは、自律神経を乱し、疲労回復を妨げます。眠っていても脳が休めていなければ、朝になってもすっきりしない状態が続きます。
こうした「脳疲労」を防ぐには、意識的に心を緩める時間を持つことが大切です。
- 仕事や家事の合間にこまめに休憩をとる
- 短時間でも外の空気を吸ったり、景色を変える
- 深呼吸、軽いストレッチ、音楽などで気分を切り替える
- 寝る前に「今日の良かったこと」を3つ書き出す
中でも、休む時間をあらかじめ予定に組み込む習慣は、疲労回復に効果的です。気持ちに余裕が生まれ、交感神経の緊張も次第に和らいでいきます。
疲れにくい体をつくる生活と食習慣
体の中から整えることも、慢性的な疲労感の改善に欠かせません。特に栄養不足やホルモンバランスの乱れは、倦怠感ややる気の低下につながります。エネルギーが不足すると、日中に必要な体力が保てなくなり、さらに疲れを感じやすくなります。
こうした不調を防ぐために、意識したい生活習慣のポイントを、以下にまとめました。
| 食事 | 主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食事を1日3回とる |
| 栄養 | 鉄分(赤身肉・レバー)、ビタミンB群(納豆・卵)、たんぱく質を意識して摂取する |
| リズム | 毎朝同じ時間に起き、朝食を欠かさない生活を心がける |
| 控えるもの | 糖分やカフェインの摂りすぎ、過度な夜更かしは避ける |
過度な食事制限や偏食は、代謝効率が落ち、エネルギー供給が低下します。まずは、しっかり食べて、決まった時間に眠る習慣を整えると、体の回復力が高まりやすくなります。
疲れが続くときに受診を検討すべきタイミング
慢性的な疲労があっても、少し休めば回復すると考えて様子を見てしまう方は多くいます。しかし、生活習慣を整えても改善しない場合は、体や心に何らかの不調が隠れている可能性があります。
次のような状態が続くときは、医療機関での相談を検討しましょう。
- 睡眠時間を確保しても疲れが抜けず、2週間以上続いている
- 食欲が落ちた、体重が減った、強いだるさがある
- 気分が落ち込む、不安や緊張が強くなってきた
- 集中できない、以前より仕事や家事に支障が出ている
- 月経の乱れや冷え、動悸、息切れなどの体調変化が見られる
これらのサインを放っておくと、症状が進み、日常生活に支障が出るおそれがあります。内科や心療内科、婦人科など、症状に応じた診療科を受診しましょう。相談先に迷うときは、近くの医療機関に加えて、オンラインで相談できるクリニックを利用する方法もあります。
まとめ
しっかり眠っても疲れが抜けないときは、睡眠の質の低下やストレスの蓄積、体内の異常などが影響している可能性があります。
セルフチェックで気になる傾向が見つかった場合は、生活習慣の改善を試みながら、必要に応じて医療機関に相談しましょう。なんとなくやり過ごすのではなく、自分の状態を見つめ直すことが、早期の回復につながります。
心と体のバランスを整える意識を持つことで、日々の疲労感が軽くなり、前向きな毎日を取り戻しやすくなります。