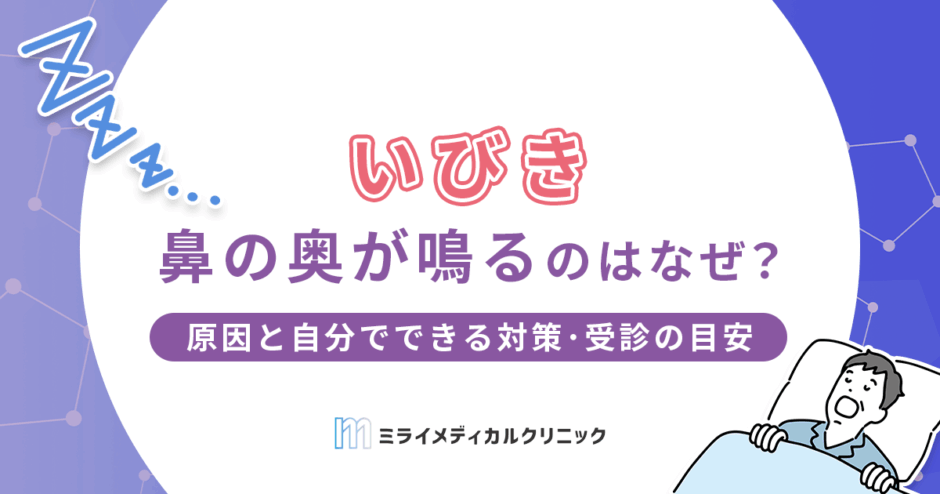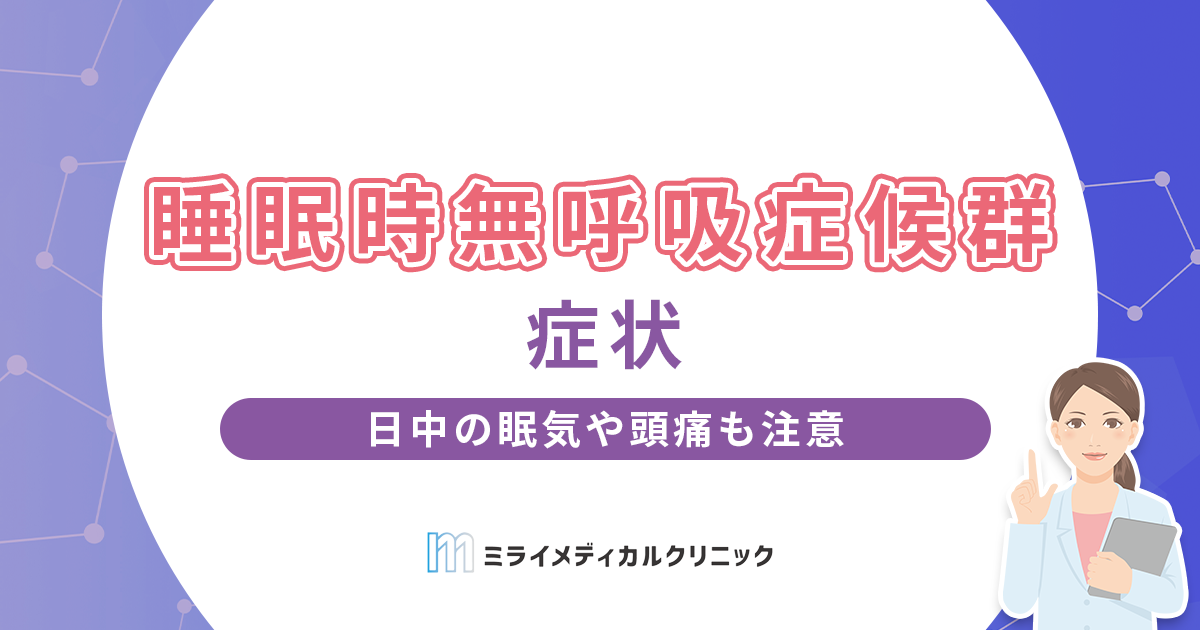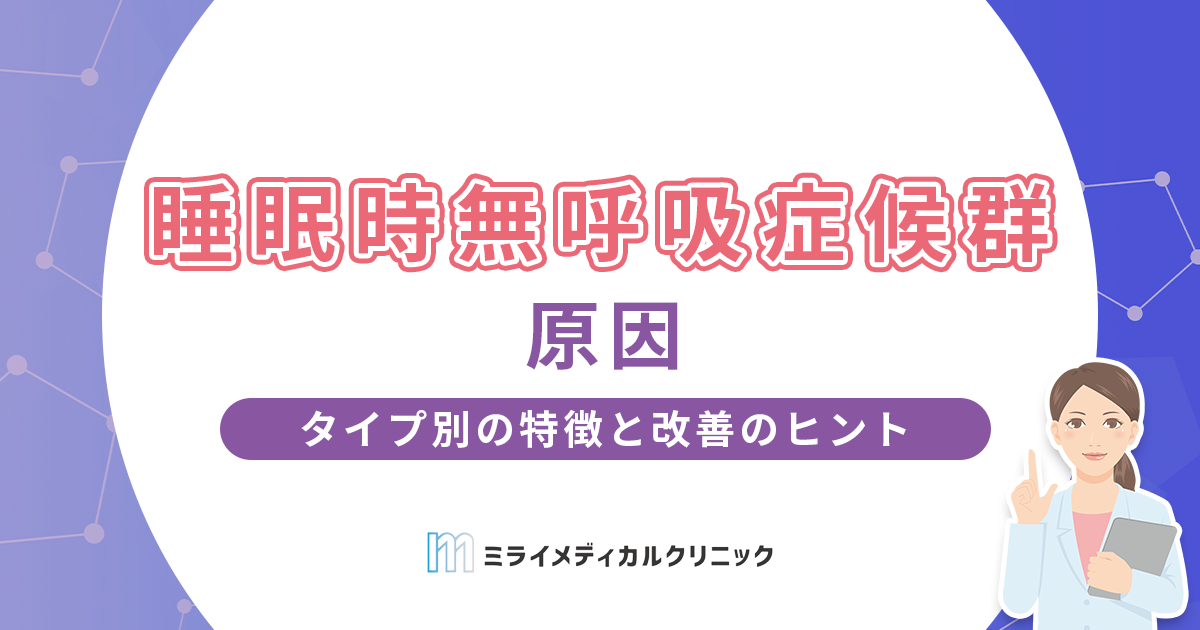寝ているとき、「鼻の奥がブーブー鳴る」「スースー音がする」と気になることはありませんか?こうした「鼻の奥で鳴るいびき」は、鼻づまりや上咽頭(鼻と喉の境目)の狭さなど、呼吸の通り道が影響していることがあります。
一時的な鼻づまりなら自宅ケアで改善できることもあります。しかし、症状が長く続く場合は睡眠の質を下げたり、無呼吸のリスクを高めたりすることもあるため注意が必要です。
この記事では、鼻の奥が鳴るいびきの原因とセルフケア、病院で相談すべき目安をわかりやすく解説します。
目次
鼻の奥が鳴るいびきとは?どの部分で音が出ているのか
鼻の奥が鳴るタイプのいびきは、喉よりも上の「鼻~上咽頭」部分で空気がうまく流れないことが原因とされています。
まずは、どこで音が出ているのか、音の特徴から原因を見分けるポイントを見ていきましょう。
鼻の奥=上咽頭や軟口蓋が振動している可能性
鼻の奥で鳴るいびきの正体は、主に「上咽頭(じょういんとう)」と呼ばれる鼻と喉の境目あたりで発生する振動音です。睡眠中は喉の筋肉がゆるむため、誰でも空気の通り道である気道が狭くなります。
この狭くなった部分を空気が通る際、周辺の粘膜や軟口蓋(なんこうがい・口の中の上あごの奥の柔らかい部分)が振動することで、いびきの音が発生します。
特に、風邪やアレルギーで鼻や喉の粘膜が腫れていると、空気の流れが乱れやすいです。その結果、「スースー」「ブーブー」といった特有の音が出ることがあります。
音の特徴でわかる!鼻の奥いびきのタイプ

鼻の奥で鳴るいびきは、音の種類によってある程度の原因を推測できます。
どんな音がしているか意識すると、セルフケアや受診の判断に役立ちます。
- スースー(高めの音):鼻づまりや粘膜の腫れによる狭窄。鼻通り改善が有効。
- ブーブー(低めの音):軟口蓋や喉の奥の振動。寝姿勢・枕調整が効果的。
- ピーピー(笛のような音):鼻ポリープや乾燥、鼻弁狭窄などが関係。医療機関での確認が必要。
自宅で簡単にできる鼻の通りチェック
鼻の通りを確認すると、いびきの原因を探る手がかりになります。
まず、片方の鼻の穴を指で軽く押さえ、もう片方の鼻でゆっくり息を吸ってみてください。左右交互に行い、どちらか一方が通りにくい・息苦しいと感じる場合は、片側の鼻づまりがある可能性があります。
また、仰向けで寝たときに鼻が詰まりやすい場合は、上咽頭の狭さや鼻粘膜のうっ血が関係していることもあります。
鼻の奥でいびきが鳴る主な原因
鼻の奥で鳴るいびきには、さまざまな要因が関係しています。一時的な鼻づまりから構造的な問題、睡眠中の呼吸状態まで幅広く、原因によって対処法も異なります。
ここでは、原因のタイプ別に、自分の症状をチェックしてみましょう。
鼻づまり・アレルギー・花粉症など一時的な要因
鼻の奥でいびきが鳴る原因で最も多いのは、一時的な鼻づまりです。アレルギー性鼻炎・花粉症・風邪などで鼻の粘膜が腫れると、空気の通り道が狭くなり、呼吸のたびに粘膜が振動して音が出やすくなります。
こうした鼻づまりはいびきの多くを占め、症状が治まれば自然に改善することが多いです。ただし、仰向けの姿勢や飲酒などの習慣が重なると、長引くこともあります。
鼻中隔の曲がりや鼻ポリープなど構造的な要因
慢性的に鼻の奥が鳴る場合は、鼻の構造そのものが関係していることもあります。代表的なのが鼻中隔湾曲症や鼻ポリープ(鼻茸)です。
鼻中隔が片側に偏っていると、片方の気道が狭くなり、空気の流れにムラが生じます。また、ポリープが鼻腔内をふさいでしまうと空気が通りにくくなり、睡眠中にいびきを引き起こします。
これらの構造的な問題は、いびきの原因として見落とされやすいです。慢性的な鼻づまりや口呼吸を引き起こすこともあります。セルフケアでの改善が難しい場合は、医師の検査を受けて原因を確かめましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が関係していることも
鼻の奥で鳴るいびきが長く続く人の中には、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が隠れているケースもあります。特に、「途中で呼吸が止まる」「日中に強い眠気がある」場合は注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群は、気道が狭くなることで呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。鼻の奥や喉の粘膜の腫れ、または肥満による気道の圧迫が関係している場合もあります。
放置すると高血圧や心疾患などにつながることがあるため、症状が続くときは医師の診断を受けましょう。
参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」
自分でできる鼻の奥いびきの対策
軽い鼻づまりや一時的ないびきであれば、生活環境の見直しで改善できる場合があります。
ここでは、鼻の奥で鳴るいびきをやわらげるために、自宅でできる簡単な対策を紹介します。
寝姿勢と枕の見直しで気道を確保
仰向けで寝ると、舌や軟口蓋が下がって鼻の奥の通り道が狭くなりやすく、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)でも同様の傾向が見られます。横向きで寝る、あるいは頭を少し高くすることで、気道を確保しやすくなります。
枕は高すぎても低すぎてもよくありません。首のカーブを自然に支える高さを意識しましょう。また、寝る直前の飲酒は喉の筋肉をゆるめ、いびきを悪化させるため控えるのが望ましいです。
鼻づまりを改善するセルフケア
一時的な鼻の奥いびきは、鼻通りを改善すると気道の通りが良くなり、いびきの軽減につながります。
次のようなセルフケアを試してみましょう。
- 部屋の加湿を保つ(湿度40〜60%が目安)
- 鼻洗浄(生理食塩水など)で花粉・ほこりを除去
- 市販の鼻腔拡張テープを就寝時に使用
- 寝る前にぬるめの蒸しタオルを鼻の上にあてて血流促進
乾燥や炎症が続くと粘膜が腫れやすくなるため、加湿と保湿を意識することが大切です。
改善しない場合は病院で相談を
鼻の奥が鳴るいびきが長く続く場合や、日中の眠気・集中力の低下を伴う場合は、医療機関への相談がおすすめです。
耳鼻咽喉科や睡眠外来では、鼻や喉の状態を詳しく調べ、原因に応じた治療法を提案してもらえます。
受診を検討すべきサイン
次のような症状がある場合は、セルフケアだけでの改善は難しい可能性があります。
- 数週間以上、鼻の奥でいびきが続く
- 呼吸が止まる、息苦しさで目が覚める
- 日中の強い眠気・頭痛・だるさがある
- 鼻づまりが慢性的で、鼻をかむ回数が多い
これらは単なるいびきではなく、鼻や喉の疾患が関係しているサインです。
医師の診断により、鼻炎・副鼻腔炎・睡眠時無呼吸症候群などの可能性を確認し、適切な治療につなげましょう。
病院で行われる主な治療の例
鼻づまりや炎症が原因の場合は、点鼻薬やアレルギー治療薬で症状を和らげることが多いです。一方で、鼻の構造に問題がある場合は、手術や器具を使った治療が行われることもあります。
また、睡眠時無呼吸症候群と診断された場合は、CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)が選ばれることがあります。この治療は、寝ている間にマスクから空気(陽圧)を送り、気道の閉塞を防ぐ方法です。いびきや無呼吸の軽減が期待されます。
いずれの場合も、自己判断で対処しようとせず、医師に相談することが大切です。
参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」
まとめ
鼻の奥が鳴るいびきは、鼻づまりや粘膜の炎症、睡眠時の姿勢などが関係しています。多くは一時的な要因で改善できますが、長く続く場合や無呼吸が疑われる場合は、早めに医師へ相談しましょう。
放置せず原因を見極めることで、睡眠の質を守り、日中のパフォーマンスも高められます。自分に合った相談先を見つけて、健康的な眠りを取り戻しましょう。