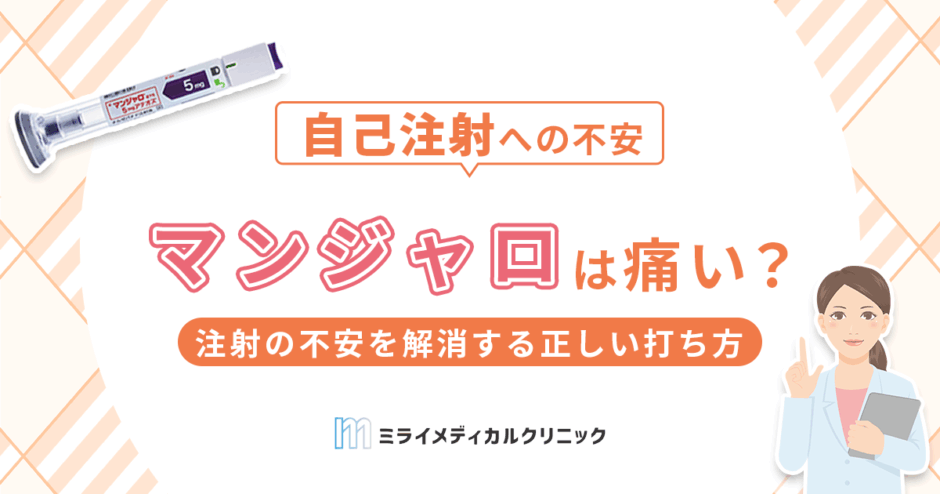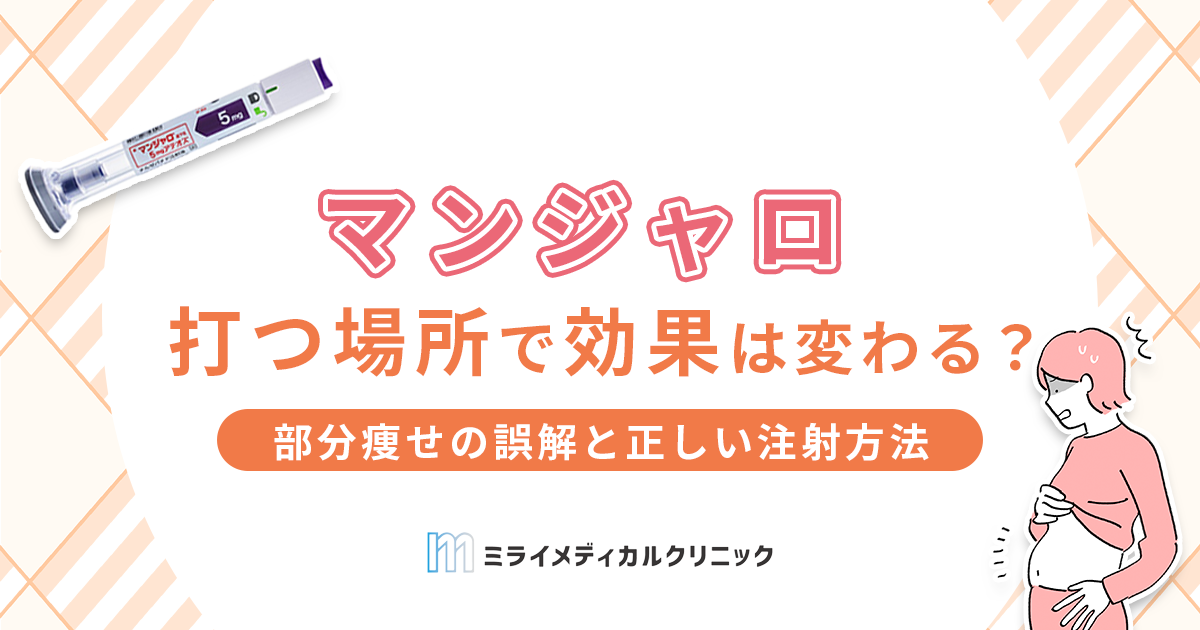「マンジャロの注射は痛いのだろうか」「自分で注射をするなんて怖くて無理」「針を刺すときの痛みが心配で治療をためらっている」そんな不安を抱えている方は決して少なくありません。注射と聞くだけで、病院での予防接種の記憶がよみがえり、痛みへの恐怖心を感じてしまうのは自然なことです。
この記事では、マンジャロ注射の実際の痛みレベルから、痛みを感じやすい場面、そして痛みを最小限に抑えるための具体的な方法まで詳しく解説します。不安を解消し、安心して治療を始められるよう、ぜひ参考にしてください。

三重大学医学部医学科を卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院にて糖尿病・代謝・内分泌内科を専門とする臨床経験を積み、専門医としての研鑽を重ねる。糖尿病、脂質異常症、甲状腺疾患、副腎疾患、骨粗鬆症などの内分泌・代謝疾患に幅広く対応し、生活習慣病を含む慢性疾患の包括的な管理に精通している。専門は「糖尿病・代謝・内分泌」。エビデンスに基づいた診療と、患者一人ひとりの生活背景を重視したきめ細やかな医療を実践している。
※本記事に掲載されている体験談や口コミは、あくまで個人の感想です。効果・効能には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。また、本記事の内容は医学的アドバイスではありませんので、使用を検討される際は必ず医師にご相談ください。
目次
マンジャロの注射針はどのくらいの太さ?
マンジャロの注射(アテオス)には、医療用の中でも極めて細い「極細針」が採用されています。針の太さはゲージ(G)という単位で表され、数字が大きいほど細くなりますが、マンジャロは29ゲージのものが使われています。
これは、糖尿病患者さんが日常的に使用するインスリン用の注射針とほぼ同じ太さです。髪の毛ほどの細さをイメージすると分かりやすいかもしれません。この設計により、注射時の痛みは大幅に軽減されており、ほとんど感じないか、チクッとする程度で済む方が大半です。ただし、痛みの感じ方には個人差があることも知っておく必要があります。
マンジャロ使用者200人にアンケート!自己注射で最も不安に感じたことは?
実際にマンジャロを使用している方は、自己注射のどのような点に不安を感じているのでしょうか。編集部がマンジャロ使用者200人に実施した独自アンケート調査では、下記のような結果となりました。

最も多かった回答は「副作用」(34.0%)で、次に「痛み」(29.0%)、そして「注射手技の失敗」(28.5%)が僅差で続きました。この結果から、約3人に1人が注射そのものの痛みを大きな不安要素として捉えていることがわかります。一方で、「針への恐怖心」(4.5%)や「注射部位の感染」(4.0%)といった不安は少数派でした。
やはり、注射という行為に伴う直接的な「痛み」と、その後の「副作用」が二大不安要素と言えるでしょう。
調査テーマ:マンジャロダイエットについて
実施期間:2025年9月6日〜2025年9月8日
調査方法:クラウドワークス
対象者:マンジャロ使用経験者(男女含む)
回答数:200名
※本アンケートは編集部が独自に実施したものです。調査内容には効果・副作用・費用・満足度などが含まれます。個人の感想や経験に基づく回答であり、効果には個人差があります。
マンジャロの自己注射で痛みを感じやすい場面
痛みの感じ方には個人差が大きいですが、いくつかの要因が重なると、通常よりも痛みを感じやすくなることがあります。どのような場面で痛みに繋がりやすいのかを理解し、それを避けることが重要です。
注射部位による違い(お腹・太もも・上腕)
マンジャロは皮膚の下にある「皮下脂肪」に注射するため、脂肪が厚く、痛みを感じる神経や毛細血管が少ない場所ほど痛みを感じにくいという原則があります。
| お腹 | 最も推奨される部位の一つです。おへその周りを避けたエリアは皮下脂肪が豊富で、多くの方が「最も痛みが少ない」と感じます。自分で注射部位を目で見て確認しやすいため、精神的な安心感にも繋がります。 |
| 太もも | 太ももの前面や外側の、比較的脂肪が多い部分も適しています。しかし、内ももなど皮膚が薄い場所や、筋肉が発達している方が脂肪の少ない部分に打つと、神経に触れてチクッとした鋭い痛みを感じることがあります。 |
| 上腕 | 肩と肘の中間あたりの、腕の後ろ側(二の腕)も注射可能ですが、自分一人で正しい位置を確認し、皮膚をしっかりつまむのが難しい部位です。そのため、角度がずれたり、筋肉に近い層に注射してしまったりして、痛みを感じやすい傾向があります。 |
角度や速度による差
注射器の扱い方も痛みに影響します。マンジャロの注射器(アテオス)は、皮膚に対して垂直(90度)に、まっすぐ押し当てるように設計されています。怖さから角度が斜めになってしまうと、針が皮下脂肪層にうまく到達せず、より痛みを感じやすい皮膚の浅い層を刺激してしまうことがあります。
また、注射の瞬間にためらい、ゆっくりと針を刺そうとすると、針が皮膚に触れている時間が長くなり、かえって痛みを意識しやすくなります。「一気に、ためらわずに」押し当てることが、結果的に痛みを最も少なくするコツです。
精神的な緊張で痛みを強く感じることも
痛みは、身体的な刺激だけでなく、心理的な状態にも大きく左右されます。「注射は痛いものだ」という強い先入観や恐怖心があると、脳は痛みの信号に対して過敏になります。これを「痛みの悪循環」と呼び、不安が体の緊張を招き、筋肉がこわばります。
硬くなった皮膚や筋肉に針を刺すと、物理的にも抵抗が大きくなり、より強い痛みとして感じてしまうのです。リラックスすることが、痛みを和らげる上で非常に重要な要素であることを覚えておきましょう。
マンジャロの自己注射で痛みを減らす工夫4選
少しの工夫と知識で、注射に伴う痛みはさらに軽減できます。これから紹介する4つのポイントを実践し、安心して治療を続けられるようにしましょう。
注射部位をローテーションする
毎回必ず注射する場所を変える「ローテーション」は、痛みを減らす上で最も重要な習慣です。同じ場所に繰り返し注射を続けると、その部分の皮下脂肪が硬くなる「リポハイパートロフィー(脂肪組織硬結)」を起こすことがあります。硬くなった皮膚は、注射時の痛みが増すだけでなく、薬の吸収が不安定になり、効果が弱まってしまう原因にもなります。
お腹を上下左右の4つのエリアに分け、「右上→左上→右下→左下」のように毎週場所を変えたり、偶数週は太もも、奇数週はお腹、といったように、自分なりのルールを決めて実践しましょう。
室温に戻してから打つ
冷蔵庫から取り出した直後の冷たい薬液は、体温との温度差から注入時に強い刺激や痛みを感じさせることがあります。これを避けるため、注射の15分〜30分前には冷蔵庫から出し、箱に入れたまま室温に馴染ませておくことを強く推奨します。
ただし、早く温めようとして手で握ったり、お湯につけたり、電子レンジで加熱したりすることは、薬の成分が変性してしまう可能性があるため絶対に行わないでください。
針をしっかり奥まで刺す(途中で止めない)
マンジャロの注射器(アテオス)は、誰でも簡単・安全に注射できるよう設計されたオートインジェクターです。皮膚に垂直に強く押し当てることで、自動的に針が適切な深さまで刺さり、薬液の注入が始まります。この時、痛みへの恐怖から途中で力を緩めてしまうと、針が中途半端な位置で止まり、かえって痛みを感じる原因となります。
「カチッ」という1回目の注入開始の音が聞こえ、その後2回目の注入完了の音が聞こえるまで、しっかりと皮膚に押し当て続けることが重要です。器具の設計を信頼し、一連の動作をためらわずに行いましょう。
リラックスした状態で注射する
心と体の緊張をほぐすことは、痛みの感じ方を大きく変えます。注射の前には、椅子に深く座り、ゆっくりと深呼吸を2〜3回繰り返してみましょう。息を吐くときに肩の力を抜くことを意識するだけでも、体はリラックスします。好きな音楽をかけたり、テレビを見たりしながら、注射という行為から意識をそらす「ディストラクション(気分転換)」も非常に有効です。
注射部位をアルコール綿で拭いた後、注射直前にその部位を短時間アイスパックなどで冷やして皮膚の感覚を少し鈍らせるのも、痛みを和らげる簡単な方法の一つです。
マンジャロの処方なら、オンライン診療のミライメディカルクリニックがおすすめ
マンジャロダイエットに関心があり、手軽に始めたいとお考えであれば、オンライン診療のミライメディカルクリニックがおすすめです。オンラインでマンジャロの診察から処方、そして薬の受け取りまでをスムーズに行えます。
自宅や職場など、場所を選ばずに医師の診察を受けられるため、医療機関への移動時間や待ち時間を気にすることなく、ご自身の都合の良い時間にオンラインで相談が可能です。これは、ダイエットを継続していく上での大きな利便性と言えるでしょう。
また、オンライン診療でありながらも、医師による丁寧なカウンセリングと診察を受けることができます。マンジャロダイエットに関する疑問や不安をじっくりと相談し、ご自身の健康状態やライフスタイルに合わせた適切なアドバイスを受けることができます。
なお、マンジャロ注射以外にも、リベルサスやメトホルミン、フォシーガなどの服用タイプの薬剤もあるため、医師と相談の上、ご自身に合ったものを検討してみてください。
まとめ|マンジャロは極細針で痛みは少ないが、不安には工夫と慣れが必要
マンジャロの注射には29ゲージの極細針が使用されており、髪の毛ほどの細さで痛みは最小限に抑えられています。しかし、マンジャロ使用者へのアンケート調査では29%の方が痛みへの不安を感じているようです。
痛みを感じやすい場面として、注射部位の選択ミス、注射角度や速度の不適切さ、精神的な緊張状態が挙げられます。特に同じ場所への繰り返し注射や、冷たい薬液での注射は痛みを増加させる要因となります。
痛みを減らすための効果的な工夫として、注射部位のローテーション、薬液を室温に戻してからの使用、針をしっかり奥まで刺すこと、リラックスした状態での注射が重要です。
マンジャロの自己注射は医療技術の進歩により、従来の注射のイメージとは大きく異なり、ほとんど痛みを感じない設計となっています。適切な知識と技術、そして心理的な準備によって、安心して治療を継続できる環境を整えることが可能です。