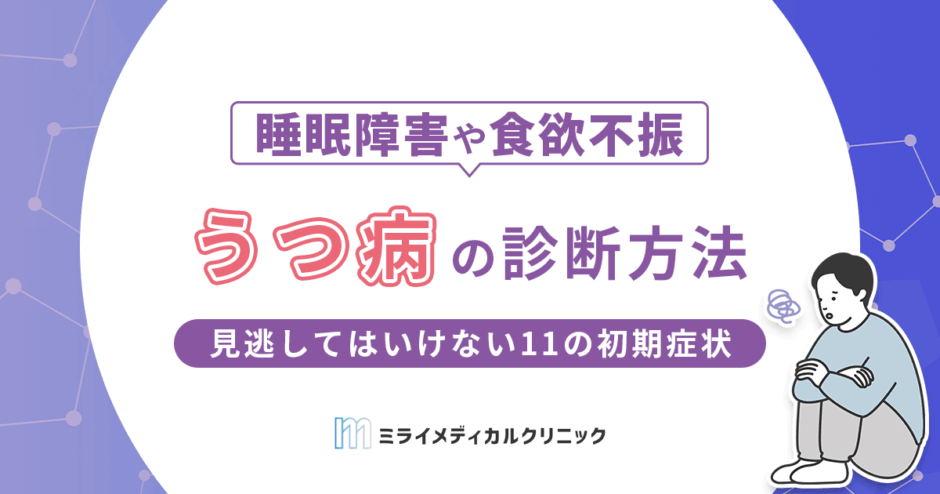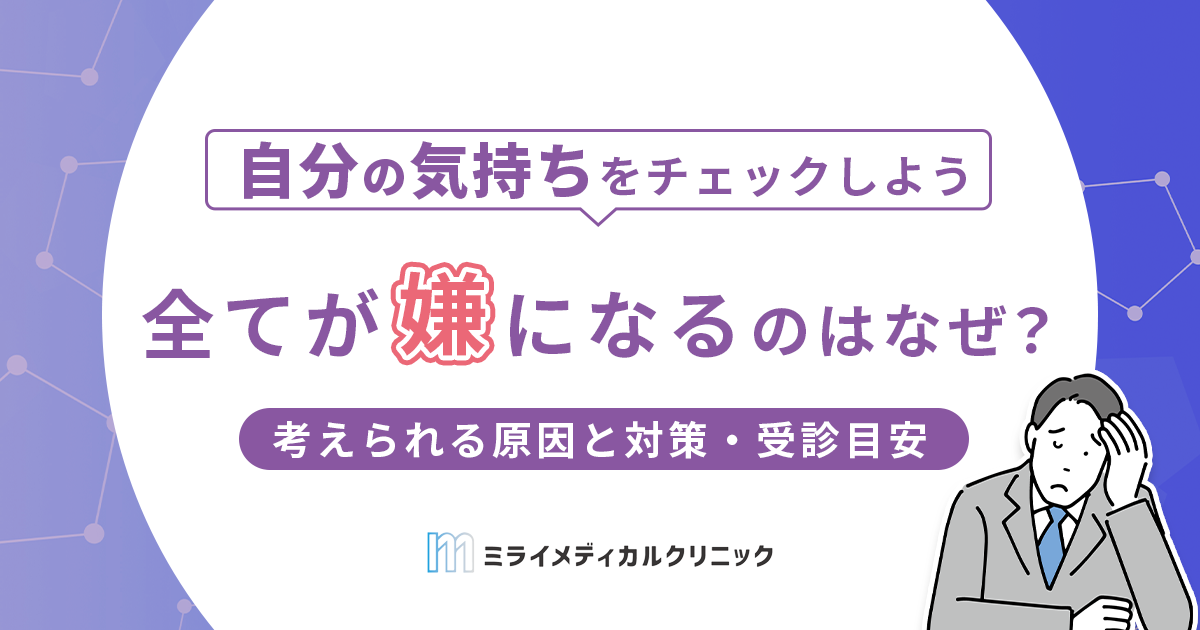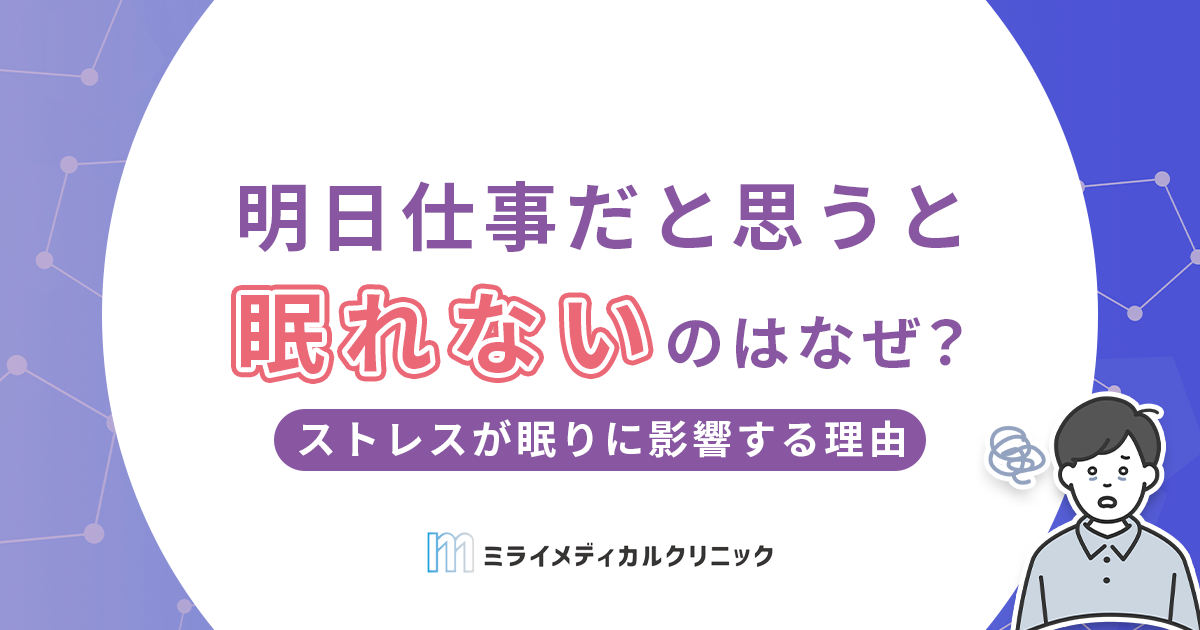「最近、なんだか気分が沈みがち…」「いつも疲れていて、何をするにも億劫…」こんな状態が続いているなら、それはただの気分の落ち込みではなく、うつ病の初期症状かもしれません。
この記事では、うつ病とはどのような病気なのか、初期症状にはどのようなものがあるのか、そして症状に気づいたらどうすべきかについて詳しく解説します。症状に心当たりがある場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談しましょう。
うつ病とはどんな病気か?心と体に現れる変化を解説
うつ病は、単なる一時的な落ち込みとは異なり、気分、意欲、思考、そして身体の機能にまで影響を及ぼし、日常生活に著しい支障をきたす可能性のある心の病気です。
適切な治療を受けることで回復が見込める病気ですが、放置してしまうと症状が慢性化したり、重症化したりすることもあります。ここでは、うつ病がどのような病気であるのか、そして心と体に現れる変化について解説します。
うつ病とは気分障害の一つで生活に支障をきたす疾患
うつ病は、気分障害という精神疾患の分類の一つです。主な症状としては、強い悲しみや憂うつな気分が持続すること、これまで楽しめていたことへの興味や喜びを失ってしまうことなどが挙げられます。
さらに、うつ病は単に気持ちが沈むだけでなく、意欲の低下、集中力や思考力の低下、決断力の低下など、精神活動全般に影響を及ぼします。「何もする気が起きない」「考えがまとまらない」「些細なことで悩んでしまう」といった状態が続くことで、仕事や学業、家事といった日常生活を送ることさえ困難になってしまうことがあります。
また、睡眠障害(不眠や過眠)、食欲不振または過食、倦怠感、頭痛、腹痛など、身体的な症状も伴うことが少なくありません。これらの症状は、周囲からは怠けているように見られたり、仮病だと思われたりすることもありますが、うつ病の症状の一つであり、決して本人の怠慢や気のせいではないことを理解することが重要です。
うつ病は、誰にでも起こりうる病気であり、決して特別なことではありません。しかし、その影響は深刻であり、早期の発見と適切な治療が不可欠です。
参考:厚生労働省「うつ病|こころの病気について知る」
一時的な落ち込みとの違いとは
誰しも気分が落ち込むことはありますが、一時的な落ち込みと、うつ病による落ち込みには違いがあります。例えば、失恋や仕事の失敗などで一時的に落ち込んだ場合は、原因が解決されたり、時間が経つにつれて自然と回復していきます。
一方、うつ病の場合は、はっきりとした原因がないのに気分の落ち込みが長く続き、日常生活に支障が出てきます。また、気分の落ち込みに加えて、興味や喜びの喪失、食欲の変化、睡眠障害、集中力の低下など、他の症状も現れることが特徴です。
以前は楽しめていた趣味や友人との会話に喜びを感じなくなったり、食欲が低下したり増加したり、眠れなくなったり、過眠になったりすることがあります。また、集中力が続かなくなり、仕事や勉強に支障が出たり、疲れやすくなり、身体がだるく感じることもあります。
このような症状が複数現れ、2週間以上続く場合は、医療機関への受診を検討することが大切です。
うつ病の初期症状が出たらどうする?診断方法を解説
うつ病の診断は、主に精神科医や心療内科医による問診と、世界的に用いられている国際的な診断基準に基づいて総合的に行われます。現時点では、うつ病を特定するための血液検査や画像検査といった客観的な検査はありません。
そのため、医師が患者さん本人やご家族から丁寧に話を聞き取ることが、診断において最も重要な情報源となります。
診断方法1|丁寧な問診による症状の確認
医師は、現在の気分の状態、睡眠や食欲の変化、日々の活動への意欲、集中力の低下、イライラ感など、心の状態だけでなく、身体に現れている症状や、日常生活への影響についても詳しく質問します。
いつから症状が現れ始めたのか、どのような時に症状が強く出るのか、過去の精神的な病気の経験や、家族歴なども確認されることがあります。ご自身の感じていることを、できるだけ具体的に医師に伝えることが大切です。
診断方法2|国際的な診断基準に基づいた評価
うつ病の診断には、主にDSM-5と、ICD-10という2つの国際的な診断基準が用いられます。
DSM-5 では、「抑うつ気分」または「興味・喜びの著しい減退」のどちらかを含む9つの症状のうち、5つ以上がほぼ毎日、2週間以上持続している場合に、うつ病と診断されることが一般的です。
ICD-10 では、抑うつ気分、興味と喜びの喪失、易疲労感の3つの主要症状のうち2つ以上と、その他の症状のうち2つ以上が、2週間以上続いている場合にうつ病と診断されます。
これらの診断基準に照らし合わせながら、医師は患者さんの訴える症状がうつ病の診断基準を満たしているかどうかを慎重に評価します。
主な症状の例(DSM-5・ICD-10に共通してみられるもの)
- 抑うつ気分(気分の落ち込み、悲しみ、憂うつ感)
- 興味または喜びの喪失(何事にも興味が持てない、楽しめない)
- 著しい体重の減少または増加、あるいは食欲不振または食欲亢進
- 不眠または過眠
- 精神運動焦燥または制止(落ち着きのなさ、または動作の緩慢さ)
- 疲労感または気力の減退(強いだるさ、疲れやすさ)
- 無価値感または過剰な罪責感(自分には価値がないと感じる、必要以上に自分を責める)
- 思考力や集中力の低下、決断困難
- 死についての反復思考、自殺念慮、自殺企図
参考:医療法人社団五稜会病院「精神科ならでは?の操作的診断とは」
診断方法3|他の病気や薬の影響の除外
うつ病と診断を下す上で、見過ごしてはならない重要なステップが、患者さんの症状が他の身体的な病気や、現在服用している薬物の影響によるものではないかを確認することです。
例えば、甲状腺機能低下症では、倦怠感、気分の落ち込み、意欲低下など、うつ病と共通する症状が見られます。また、一部の薬剤やアルコール、薬物の使用も、気分の変動や睡眠障害、食欲不振といったうつ病に似た症状を引き起こすことがあります。
そのため、医師は患者さんの病歴や現在服用している薬、飲酒や喫煙、薬物使用の状況などを詳しく問診し、必要に応じて血液検査や画像検査などの追加の検査を行うことがあります。
これにより、うつ病の症状が他の疾患や物質の影響によるものではないことを慎重に確認し、正確な診断へと繋げていきます。この除外診断は、適切な治療方針を決定する上で非常に重要なプロセスとなります。
うつ病の初期症状とは?見逃してはいけない11の兆候
うつ病は、心の風邪と言われることもありますが、早期発見と適切な対応が非常に重要です。初期症状を見逃さず、早めに専門家に相談することで、症状の悪化を防ぐことができます。
初期症状1|睡眠の異変(眠れない・途中で目が覚める・早朝に起きる)
うつ病の初期症状として、睡眠の異変がよく見られます。なかなか寝付けなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったり、朝早くに目が覚めてしまい、その後眠れなくなるといった症状が現れることがあります。
例えば、今までぐっすり眠れていたのに、最近寝つきが悪くなった、夜中に何度も目が覚めるようになった、朝早く目が覚めてしまい二度寝できない、といった場合は注意が必要です。
初期症状2|食欲や体重の異変(食欲不振または過食による体重変化)
食欲の変化も、うつ病の初期に見られる重要なサインです。人によっては、極端に食欲が低下し、何を食べても美味しく感じられず、結果として体重が減少することがあります。一方で、ストレスや不安から逃れるように過食に走り、以前よりも明らかに食事量が増え、体重が増加するケースも見られます。
このように、食欲不振と過食という相反する症状のどちらが現れるにしても、通常時からの明らかな変化には注意が必要です。
初期症状3|活動に対する興味や喜びが消える
これまで熱心に取り組んでいた趣味や、楽しみにしていた活動に対して、急に興味や関心が薄れてしまうのは、うつ病の初期症状としてよく見られます。
「何をやっても楽しくない」「何をしても心が満たされない」といった感情は、うつ病の兆候である可能性があります。もし、以前は当たり前に感じていた喜びや楽しみが失われ、生活の彩りが薄れてしまったように感じる場合は、自身の心の状態を観察することが大切です。
初期症状4|気分が沈み、悲しみやむなしさにとらわれる
持続的な気分の落ち込みや、理由もなく悲しみやむなしさに襲われるといった感情は、うつ病の核となる症状の一つです。一時的な憂鬱感とは異なり、これらの感情は長く続き、日常生活の様々な場面で影響を及ぼします。
「いつも心が重い」「涙もろくなった」「何を見ても悲しい気持ちになる」といった状態が続く場合は、単なる一時的な感情の波と捉えずに、うつ病の初期症状である可能性を考慮する必要があります。特に、これらの感情が数週間以上持続し、改善の兆しが見られない場合は、専門家へ相談しましょう。
関連記事:「涙が止まらない精神状態って病気?考えられる要因と対処法を紹介」
初期症状5|集中力の低下やミスの増加
精神的な活動の低下も、うつ病の初期症状として現れることがあります。集中力が持続しにくくなり、仕事や勉強、家事など、これまで難なくこなせていた作業でミスが増えることがあります。
例えば、会議中に話の内容が頭に入ってこない、簡単な計算を間違えてしまう、書類の整理に時間がかかるようになるなど、些細なことから業務に支障をきたすようなことまで、様々な形で現れます。
もし、以前は問題なくできていたことが困難に感じられるようになったり、注意力が散漫になったと感じる場合は、うつ病の初期症状である可能性を考慮し、無理せず休息を取ることも重要です。
初期症状6|イライラや落ち着きのなさ
気分の落ち込みと並行して、些細なことに対して過敏に反応し、イライラしたり、理由もなく落ち着かずにそわそわしたりするのも、うつ病の初期症状として見られることがあります。
普段は穏やかな性格の人が、些細なことで感情的に怒りっぽくなったり、常に焦燥感を感じて落ち着いていられないといった変化は、周囲の人も気づきやすいサインかもしれません。
このような感情の不安定さは、人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があるため、もし自身や周囲の人がこのような変化に気づいた場合は、注意深く見守り、必要であれば専門家の支援を検討することが大切です。
初期症状7|理由のない罪悪感・無力感・無価値観
うつ病の初期段階では、客観的に見れば何の問題もない状況であるにもかかわらず、自分自身を責めてしまうような罪悪感や、何をしても無駄だと感じる無力感、自分には価値がないと感じてしまう無価値観に苛まれることがあります。
これらの感情は、自己肯定感を著しく低下させ、さらに気分の落ち込みを深める悪循環を生み出す可能性があります。「自分が悪い」「周りの人に迷惑をかけている」「自分なんていてもいなくても同じだ」といった考えが頭から離れない場合は、うつ病の初期症状である可能性を考慮しましょう。
初期症状8|涙もろくなる・感情が抑えきれない
感情のコントロールが難しくなるのも、うつ病の初期症状の一つです。些細なことで涙がこぼれてしまったり、悲しみや怒り、不安などの感情がこみ上げてきて抑えきれなくなったりすることがあります。これまで感情の起伏が少なかった人が、急に涙もろくなったり、感情の波が激しくなった場合は、心身のバランスが崩れているサインかもしれません。
このような感情の変化は、本人にとっても辛く、周囲とのコミュニケーションにも影響を与える可能性があるため、もしこのような状態が続くようであれば、専門家のサポートを求めることが大切です。
関連記事:「少し言われただけで泣くのは病気?涙もろさの原因や対処法を紹介」
初期症状9|身体のだるさ・倦怠感が続く
精神的な症状に加えて、身体的な症状が現れるのも、うつ病の初期症状の特徴です。十分な睡眠をとっているにもかかわらず、朝起きても疲れが取れていなかったり、常に身体が重く感じられたりする倦怠感が続くことがあります。これは、単なる肉体的な疲労とは異なり、精神的なエネルギーの低下が身体に影響を及ぼしていると考えられます。
「何をするにも億劫」「体が鉛のように重い」といった感覚が続く場合は、無理に頑張ろうとせず、休息を心がけ、必要であれば医療機関への受診を検討しましょう。
初期症状10|原因のはっきりしない痛みや頭痛・肩こりなどの身体症状
うつ病は、精神的な症状だけでなく、様々な身体的な症状を引き起こすことがあります。原因がはっきりとしないにもかかわらず、頭痛や肩こり、腹痛、腰痛、関節痛など、様々な部位に痛みが現れることがあります。
病院で検査を受けても特に異常が見つからないのに、体の不調が続く場合は、うつ病の初期症状の一つとして考慮する必要があるでしょう。これらの身体症状は、精神的な苦痛をさらに増幅させる可能性があるため、もし長引く体の不調に悩んでいる場合は、心身両面からのアプローチが必要となるかもしれません。
初期症状11|自殺願望・死にたい気持ちの出現
最も深刻な初期症状の一つが、死にたい気持ちや自殺願望の出現です。これは、うつ病が進行し、精神的な苦痛が限界に達しているサインであり、決して見過ごしてはならない危険な状態です。「生きていても仕方がない」「消えてしまいたい」といった考えが頭から離れない場合は、ためらわずにすぐに専門機関に相談する必要があります。
一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人、医療従事者に助けを求め、適切な支援を受けることが必要です。
うつ病の診断方法と初期症状まとめ
うつ病は単なる一時的な落ち込みとは異なり、気分、意欲、思考、身体機能に影響を及ぼす気分障害の一種です。
早期発見と適切な治療が重要であり、放置すると慢性化や重症化のリスクが高まります。初期症状としては、睡眠の異変、食欲や体重の変化、興味や喜びの喪失、持続的な気分の落ち込み、集中力低下、イライラ感、罪悪感や無価値観、感情のコントロール困難、身体のだるさや原因不明の痛み、そして最も深刻な症状として自殺願望などが挙げられます。
うつ病の診断は、精神科医や心療内科医による丁寧な問診と、DSM-5やICD-10といった国際的な診断基準に基づいて行われます。主要な症状が2週間以上持続し、日常生活に支障をきたしている場合、うつ病と診断される可能性があります。また、甲状腺機能低下症など他の身体疾患や薬物の影響を除外することも重要な診断プロセスです。
症状に心当たりがある場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが大切です。