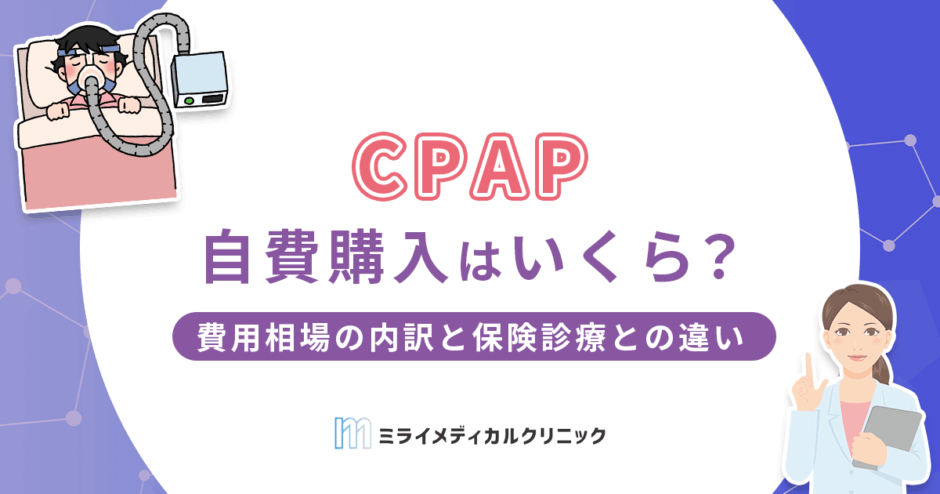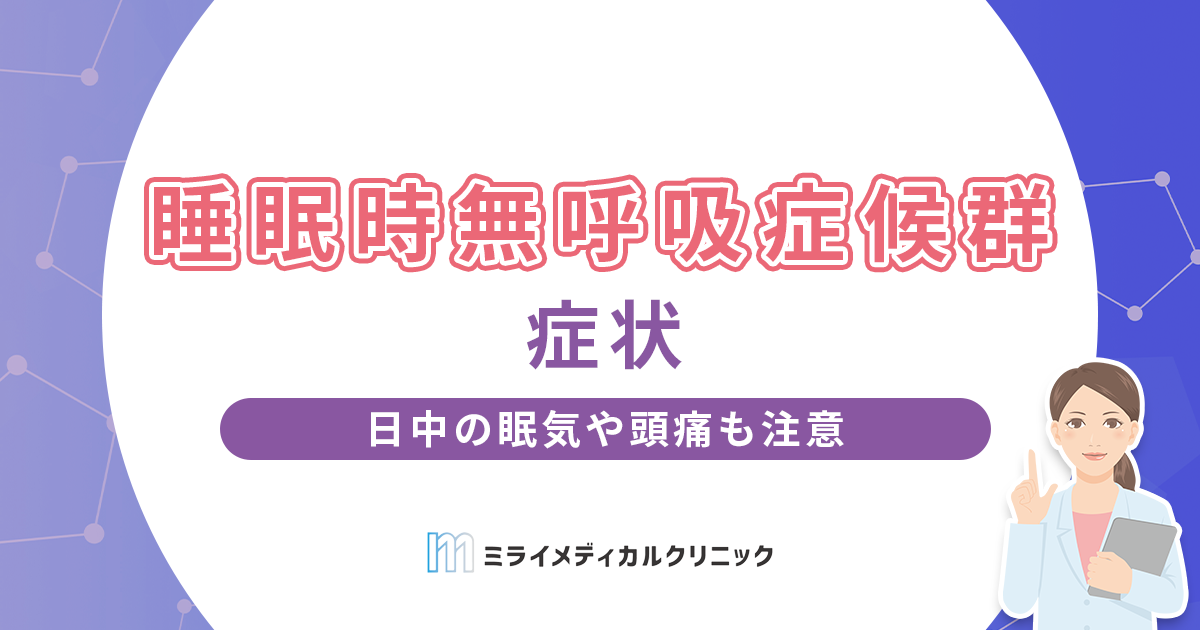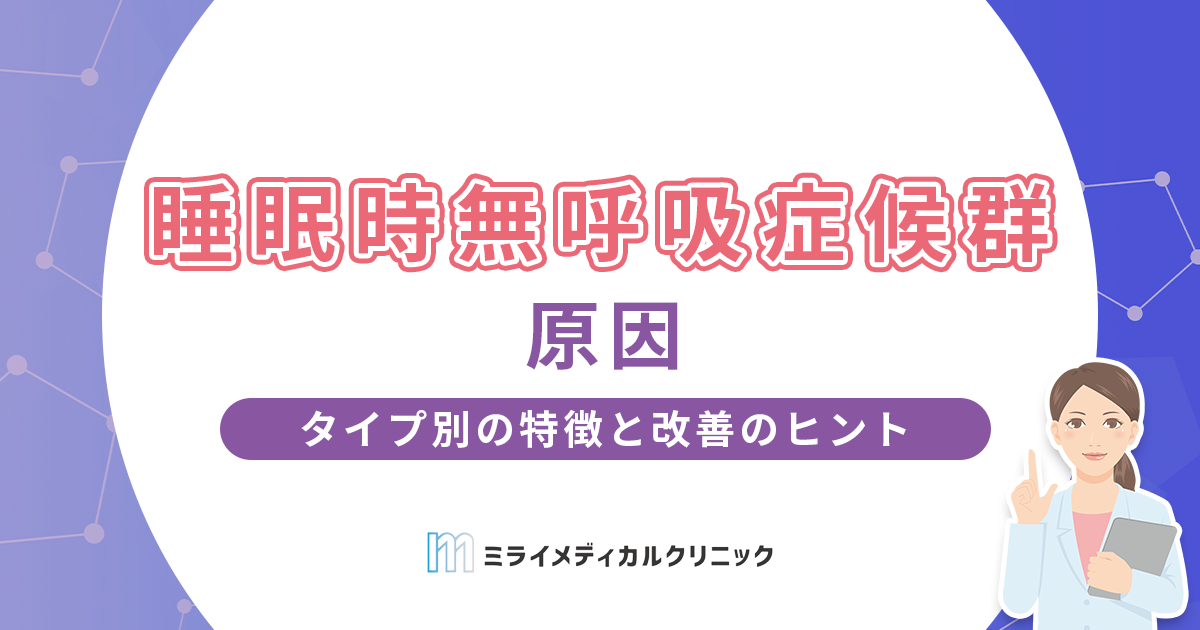「CPAPを自分で購入したいけれど、いくらかかるの?」「保険診療と自費購入、どちらが自分に合っているのか知りたい」という方も多いはず。CPAP療法を始める際、費用負担の方法は大きく分けて「保険診療」と「自費購入(自由診療)」の2種類があり、保険が適用されるか否かで導入の手順や月々のコスト、医療機関との関わり方が大きく異なります。
この記事では、CPAPの自費購入と保険診療の違いから、自費購入の詳しい費用相場と内訳、メリット・デメリット、3つの購入方法、購入時の注意点まで包括的に解説します。費用と安全性を両立させた最適な選択をするための参考にしてください。
目次
CPAPの自費購入とは?保険診療との違い

プログラム・抄録集」
CPAP療法を始める際、費用負担の方法は大きく分けて「保険診療」と「自費購入(自由診療)」の2種類があります。保険が適用されるか否かで、導入の手順や月々のコスト、医療機関との関わり方が大きく異なります。
(参考:日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020」)
保険診療のCPAPはレンタルが基本
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、AHI(無呼吸低呼吸指数)が一定の基準を満たす場合、健康保険が適用されます。保険診療におけるCPAP治療は、機器を購入するのではなく、医療機関から「レンタル」するのが基本です。
この場合、医師の診断と、治療効果の確認や指導を受けるための定期的な通院(通常は月1回)が条件となります。費用は3割負担の方で、診察料や管理料、レンタル料を含めて月額約4,000円から5,000円前後で利用可能です。
参考:厚生労働省「医療技術再評価提案書(保険既収載技術用)」
自費購入は「自由診療扱い」
一方、保険適用の基準を満たさない軽症の方や、定期通院が難しい方、特定の最新機種を使いたい方などのために、CPAP装置を全額自己負担で購入する方法もあります。これは「自由診療扱い」となり、医師の診断書が不要なため、個人輸入やインターネット通販サイトなどを通じて入手することも可能です。
ただし、保険診療と異なり、機器の圧設定や使用状況のデータ確認といった医療管理・フォローアップもすべて自己責任となる点に注意が必要です。
CPAPを自費で購入する場合の費用相場
CPAP装置を自費で購入する場合、その費用は機種や購入方法によって幅があります。装置一式で20万円から50万円程度が目安とされていますが、フィルター交換やクリーニングなどの年間メンテナンス費用が約1万円程度かかることも考慮しなければなりません。
より具体的な内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 費用目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 本体価格 | 80,000〜150,000円程度 | 家庭用CPAP装置(ResMed、Philipsなど) |
| マスク | 10,000〜30,000円程度 | 鼻マスク・フルフェイス型など |
| チューブ・加湿器 | 5,000〜15,000円程度 | 消耗品(別売の場合あり) |
| 年間メンテナンス | 10,000円程度 | フィルター交換・クリーニングなど |
CPAPの自費購入は、合計で 10万〜20万円程度が目安ですが、静音性や携帯性に優れた最新の高性能モデルでは、総額が25万円を超えることもあります。
CPAPを「自費レンタル」する場合の費用
購入には至らなくても、保険適用外でCPAPを試したい場合、「自費レンタル」という選択肢もあります。このサービス形態は、提供元によって費用や特徴が異なります。
| サービス形態 | 費用/月額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自費レンタル(医療機関) | 8,000〜10,000円程度 | 医師管理あり、自由契約可 |
| 自費レンタル(通販業者) | 5,000〜8,000円程度 | 自宅利用可、診断書不要 |
| 保険レンタル(参考) | 4,500〜5,000円程度 | 医師の診断+定期通院が必要 |
短期間の利用やお試しであればレンタル、通院の手間を省き自宅で管理したい場合は購入が向いていると言えるでしょう。
CPAPを自費購入するメリットとデメリット
CPAPの自費購入は、保険診療(レンタル)にはない利点がある一方で、特有の注意点も存在します。導入を検討する際は、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。
CPAPを自費購入するメリット
- 医師の診断なしで導入可能
- 自宅で自由に使用できる
- 継続コストが抑えられる(長期的に見ればお得)
自費購入の最大のメリットは、その自由度の高さにあります。保険適用に必要な医師の診断なしで導入が可能なため、検査結果が基準に満たなかった方でも治療を開始できます。
また、月1回の定期通院の義務がなく、自宅で自由に使用できる点も大きな利点です。初期費用は高額になりますが、月々のレンタル料が発生しないため、長期的に見れば継続コストを抑えられる可能性があります。
CPAPを自費購入するデメリット
- 医師による圧設定・効果確認ができない
- 故障・異常の際に自己対応が必要
- 医療保険のサポートが受けられない
一方で、デメリットも明確です。最も大きな点は、医師による専門的なサポートが受けられないことです。保険診療であれば医師が行う適切な圧設定や、睡眠データに基づく治療効果の確認ができません。
万が一、機器が故障したり使用中に異常を感じたりした場合も、すべて自己対応が必要です。当然ながら、自由診療のため医療保険のサポートは一切受けられず、全額が自己負担となります。
CPAPを自費購入する方法3選
CPAP装置を自費で購入する場合、主に3つのルートが考えられます。それぞれ価格やサポート体制が異なるため、自身の状況に合わせて選ぶ必要があります。
方法1| 医療機器販売業者・通販サイトで購入
一つ目は、国内の医療機器販売業者や、その代理店が運営する通販サイトで購入する方法です。
ResMed社やPhilips社製の正規品を取り扱っている国内代理店もあり、日本語でのサポートが期待できます。また、Amazonや楽天市場などの大手通販モールでも、並行輸入品などが販売されているケースがあります。
方法2|海外通販(個人輸入)
二つ目は、海外の通販サイトなどを利用し、個人輸入の形で直接購入する方法です。
国内で購入するよりも価格が安い傾向にありますが、外国語でのやり取りが必要になるほか、万が一の故障時に保証や修理サポートが受けにくいというリスクを伴います。また、医療機器として税関で手続きが必要になったり、輸入が差し止められたりする可能性もゼロではありません。
方法3|医療機関・クリニック経由での販売
三つ目は、CPAP治療を行っている医療機関やクリニック経由で自費購入する方法です。
価格は通販サイトなどより高くなる可能性がありますが、医師による適切な圧設定や使用方法の指導、アフターケアといったサポートが付属している場合が多く、安全性を重視する方にとっては安心な選択肢です。最近では、オンライン診療で自費購入に対応する施設もあります。
CPAPを自費で購入する際に注意すべきポイント
- 海外製は電圧・コンセント形状に注意
- マスクの形状・サイズは必ず確認
- 圧設定を自分で調整する場合は慎重に(過圧のリスクあり)
- 定期的な清掃・消耗品交換が必要
CPAPを自費で購入する際は、安全かつ効果的に使用するためにいくつかの点に注意が必要です。特に海外から個人輸入する場合は、電圧やコンセントの形状が日本国内の仕様と合っているかを必ず確認してください。
また、マスクは治療効果を左右する重要なパーツであるため、自分の顔の形や鼻の高さに合った形状・サイズを選ぶことが不可欠です。医師の指導なしに圧設定を自分で行う場合は、圧が強すぎると(過圧)、かえって睡眠を妨げたり不快感を引き起こしたりするリスクがあるため、慎重に行う必要があります。
参考:PMC「閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者における持続陽圧呼吸療法の臨床的副作用」
まとめ|CPAPの自費購入は初期費用10〜20万円で長期的にはコスト削減も
CPAPの費用負担方法は保険診療(レンタル)と自費購入(自由診療)の2種類があります。保険診療は月1回の定期通院が条件でレンタル料を含めて月額4,000〜5,000円程度(3割負担)ですが、自費購入は全額自己負担で装置一式20〜50万円が目安です。
自費購入の費用内訳は、本体価格が80,000〜150,000円、マスクが10,000〜30,000円、チューブ・加湿器が5,000〜15,000円、年間メンテナンス費用が約10,000円で、合計10〜20万円程度が目安ですが、高性能モデルでは総額25万円を超えることもあります。自費レンタルという選択肢もあり、医療機関経由で月額8,000〜10,000円、通販業者経由で月額5,000〜8,000円程度です。
自費購入のメリットは、医師の診断なしで導入可能、月1回の定期通院義務がなく自宅で自由に使用できる、初期費用は高額だが長期的には継続コストを抑えられる点です。一方デメリットは、医師による圧設定・効果確認ができない、故障時に自己対応が必要、医療保険のサポートが受けられない点です。
購入方法は、国内の医療機器販売業者・通販サイト、海外通販・個人輸入、医療機関・クリニック経由の3つがあります。購入時は電圧・コンセント形状の確認、マスクのサイズ選択、過圧リスクに注意した圧設定、定期的な清掃・消耗品交換が重要です。