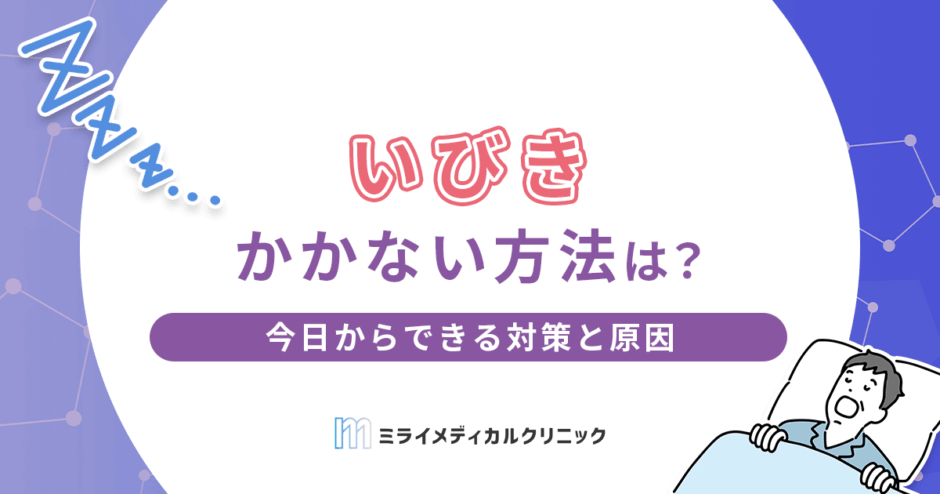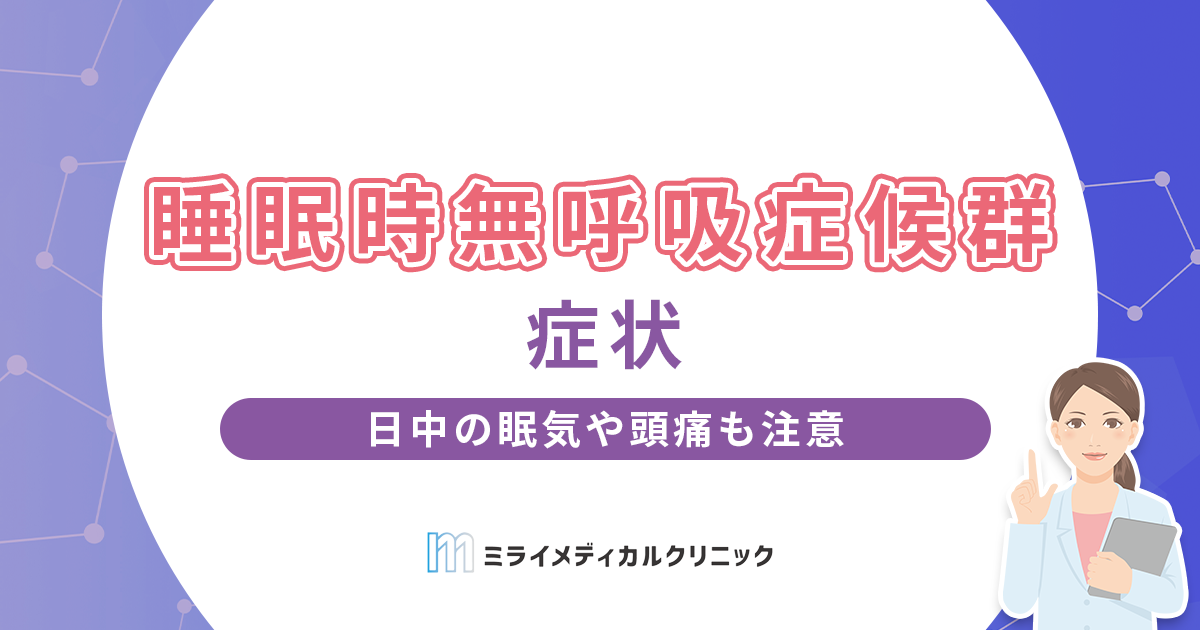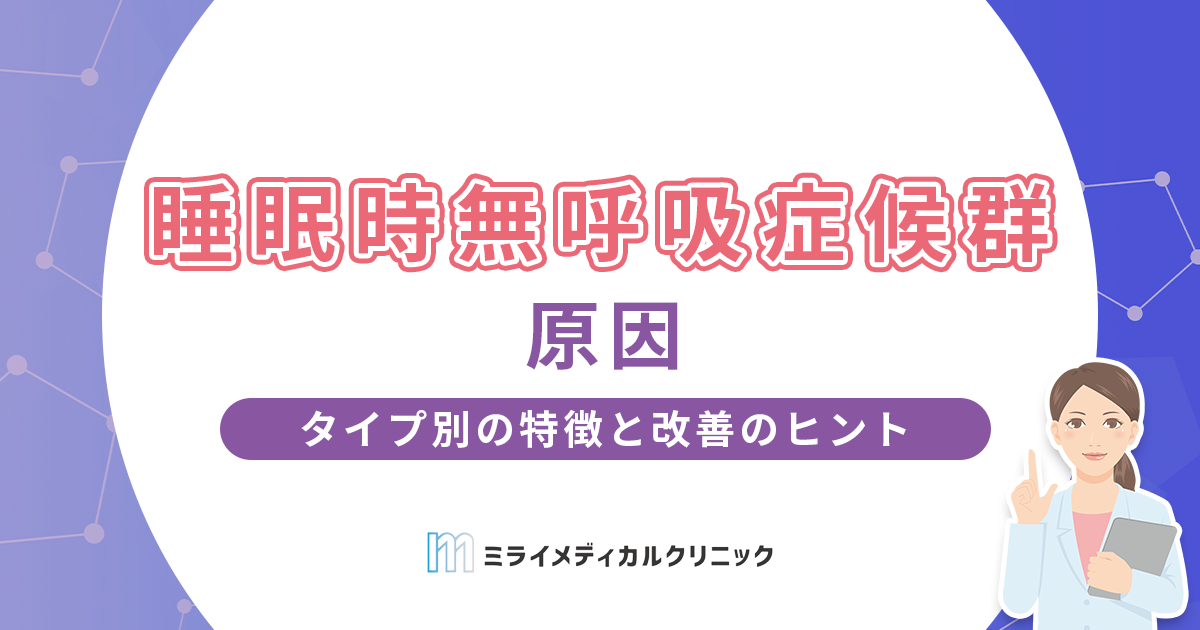パートナーや家族からいびきを指摘されると、「疲れているだけ」と思いがちです。しかし、いびきをそのままにしておくと睡眠の質が下がり、日中の集中力不足や体調不良につながることもあります。
多くのいびきは、生活習慣や寝るときの姿勢を見直すことで改善が期待できますが、なかには睡眠時無呼吸症候群など病気が隠れているケースもあるため注意が必要です。
この記事では、今日からすぐに試せるいびきを防ぐ方法と、医師に相談すべきサインについて解説します。
目次
いびきをかかないためにまず知っておきたい基本
いびきをなくすためには、まず「なぜいびきが起こるのか」を理解することが大切です。原因を知ることで、どんな対策を選べばよいかが見えてきます。
ここでは、いびきの仕組みと主な原因を見ていきましょう。
いびきはどうして起こるの?
いびきは、寝ている間に空気の通り道である「気道」が狭くなることで発生します。狭くなった場所を空気が無理に通ろうとするときに、のどや鼻の粘膜・舌の付け根などが振動し、その音が「いびき」として聞こえる仕組みです。
起きているときは筋肉が気道を支えているため、空気はスムーズに通ります。しかし、睡眠中は筋肉がゆるむため、舌やのどの組織が下がって気道が狭くなりやすいです。
また、慢性的ないびきは、睡眠時に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」のサインかもしれません。体に十分な酸素が行き渡らなくなり、健康に影響をおよぼすため注意が必要です。
参考:日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)」
いびきを招く主な原因
いびきの原因は一つではなく、複数の要因が重なって起こることがほとんどです。
主な原因としては、肥満・口呼吸・仰向け寝・飲酒・加齢が挙げられます。
特に肥満で首まわりに脂肪がつくと気道が圧迫されやすく、仰向けで寝ると舌がのどの奥に下がりやすくなるため、いびきのリスクが高まります。また、アルコールを飲むと筋肉がゆるみやすくなるため、飲酒後のいびきは大きくなりがちです。
このように、原因によって対策の方向性も変わってきます。
例えば、肥満が原因なら体重管理を、鼻づまりによる口呼吸が原因なら鼻呼吸の改善を目指すのが効果的です。自分の生活習慣を振り返り、当てはまる原因を探ってみましょう。
| 主な原因 | 対策の方向性 |
|---|---|
| 肥満 | 首周りの脂肪を減らすための体重管理 |
| 口呼吸 | 鼻づまりの改善、口を閉じる習慣づけ |
| 仰向け寝(閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の場合) | 横向きで寝る習慣をつける |
| 飲酒 | 寝る前の飲酒を控える、量を減らす |
| 加齢 | のどの筋肉を鍛えるトレーニング |
睡眠アプリでいびきの傾向をチェックしてみよう
いびきの改善には、まず自分の「いびきの状態」を知ることが大切です。最近では、スマートフォンのアプリを使って簡単に睡眠中のいびきを記録・分析できます。
ここでは、アプリの使い方と精度について紹介します。
睡眠アプリでできること
自分のいびきがどの程度のものなのか、客観的に知るのは難しいものです。そこで役立つのが、スマートフォン向けの睡眠アプリです。多くのアプリには、寝ている間のいびきをマイクで録音し、分析してくれる機能がついています。
アプリを使うと、いびきの音量や時間帯を自動で記録し、グラフで確認できます。これにより、「自分では気づいていないいびき」の状態を目で見て確認が可能です。
セルフケアを始めた後にいびきがどう変化したかを記録できるため、対策の効果を判断する上でも役立ちます。まずは自分のいびきの傾向を知るために、アプリを活用してみるのがおすすめです。
研究でわかったスマホアプリの精度
-1-1024x538.png)
スマートフォンのアプリで、いびきをどれだけ正確に検知できるのか気になる人もいるでしょう。
Brown(2025)は、擬似的な実環境で特定アプリのいびき検出アルゴリズムを検証し、感度86.3%・特異度99.5%・総合精度95.2%と報告しています。これは、生活音との区別が一定の精度で可能であることを示した実験的データです。
ただし、臨床下での診断精度を直接示すものではなく、あくまでいびき傾向を把握する参考ツールとして活用するのが適切です。
出典:PMC「Accuracy of Smartphone-Mediated Snore Detection in a Simulated Real-World Setting」(Brown 2025)
今夜から試せる!いびきをかかないための即効対策
自分のいびきの傾向をつかんだら、次は実際の対策です。難しい器具を使わなくても、寝る姿勢や環境を少し工夫するだけで改善が見られることもあります。
ここでは、今夜からできる簡単な方法を紹介します。
寝る姿勢を変えて気道を広げる
いびきを軽減するために、今夜からすぐに試せる最も簡単な方法が「寝る姿勢を変える」ことです。特に、仰向けで寝る習慣がある方は、横向きで寝るよう意識するだけで改善するケースもあります。
仰向けでは重力の影響で舌がのどの奥へ下がりやすく、気道が狭くなりやすくなります。これは閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)にも見られる特徴で、いびきの主な原因の一つです。横向きで寝ることで舌の落ち込みを防ぎ、空気の通り道を確保しやすくなります。
抱き枕を使ったり、背中にクッションを置いたりすると、自然に横向きの姿勢を保ちやすくなります。枕は首(頸椎)がまっすぐ保てる高さを選びましょう。高すぎても低すぎても気道が圧迫され、いびきを悪化させるおそれがあります。
鼻呼吸を促す工夫を取り入れる
いびきの原因として、口で呼吸する「口呼吸」も大きく関係しています。鼻呼吸に比べて口呼吸は舌がのどの奥へ下がりやすく、空気がのどを直接刺激して乾燥させるため、いびきを悪化させやすいです。いびきを防ぐためには、できるだけ鼻呼吸を意識するとよいでしょう。
また、鼻うがいなどで鼻の通りを良くしておくことも大切です。花粉症やアレルギー性鼻炎などで慢性的に鼻が詰まっている場合は、耳鼻咽喉科で治療を受けることが根本的な解決につながります。鼻づまりが解消されるだけで、いびきが改善するケースもあります。
寝室環境を整えて呼吸しやすくする
寝室の環境も、いびきに影響をおよぼす要素の一つです。特に空気が乾燥していると、のどや鼻の粘膜が乾き、炎症で気道が狭くなりやすくなります。
湿度は40〜60%(上限は60%目安)が参考になります。乾燥で粘膜が荒れる一方、高湿はカビ・ダニのリスクがあるため、季節に応じて調整が必要です。
また、室温はおおむね18〜24℃の範囲で快適な人が多く、高齢者では20〜25℃が適するとの報告もあります。個人差が大きいため、1℃ずつ調整して最適点を探りましょう。
空気清浄機を使ってホコリやアレルゲンを取り除き、清潔で快適な呼吸ができる環境を整えることも、いびき対策として有効です。
セルフケアで改善しないときは医師へ相談を
生活習慣を見直してもいびきが続く場合、体の内部に原因が隠れている可能性があります。
特に「呼吸が止まる」「強い眠気がある」といった症状がある場合は、医療機関での検査を検討しましょう。
受診の目安になるサイン
セルフケアを続けてもいびきが改善しない場合は、生活習慣以外の要因が関係している可能性があります。特に注意したいのは、睡眠中に呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群の可能性です。
日中に強い眠気が続いたり、朝の頭痛や集中力低下が見られたりする場合は、睡眠の質が大きく下がっているサインです。家族やパートナーから「呼吸が止まっている」と指摘された場合も、早めに呼吸器内科や耳鼻咽喉科、睡眠外来などで相談してみましょう。
医療機関で行われる主な検査と治療
医療機関ではまず、問診と検査でいびきの原因を調べます。自宅で行う簡易検査のほか、病院に一泊して行う精密検査(PSG)で、睡眠中の呼吸の状態や無呼吸の回数を確認します。
治療は、症状の程度や原因に応じて選ばれ、軽症ではマウスピース療法、中等症以上ではCPAP(シーパップ)療法が一般的です。CPAPは鼻にマスクを装着し、一定の空気圧で気道の閉塞を防ぐ方法です。
多くの場合に保険が適用され、自宅で継続して使うことでいびきや日中の眠気の改善が期待できます。
参考:日本呼吸器学会「Q30. CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」
まとめ
いびきは生活習慣の改善や寝る姿勢の見直しで軽減できるケースが多く、横向き寝や湿度管理、飲酒の制限などは効果的な方法です。アプリを使っていびきの傾向を「見える化」することも、セルフケアの第一歩になります。
一方で、日中の眠気や集中力の低下、呼吸の停止などが見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。自己判断で放置せず、専門医に相談して原因を明確にすることが大切です。