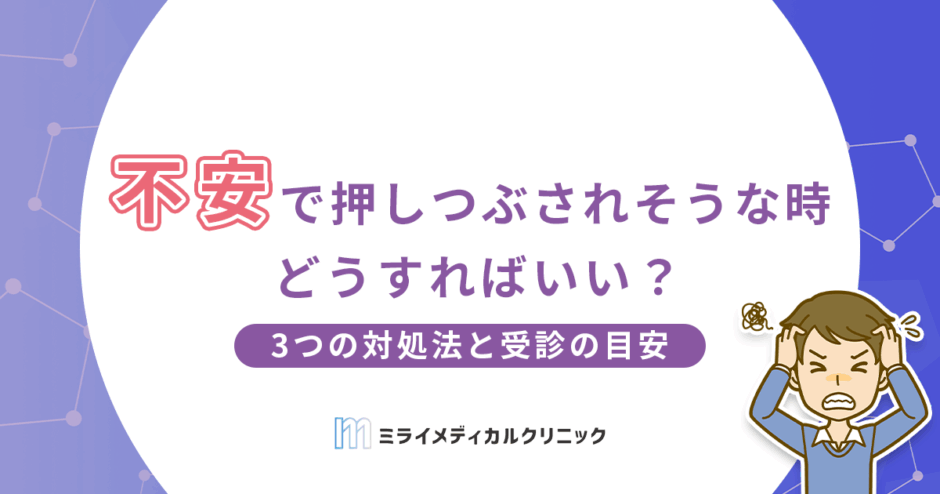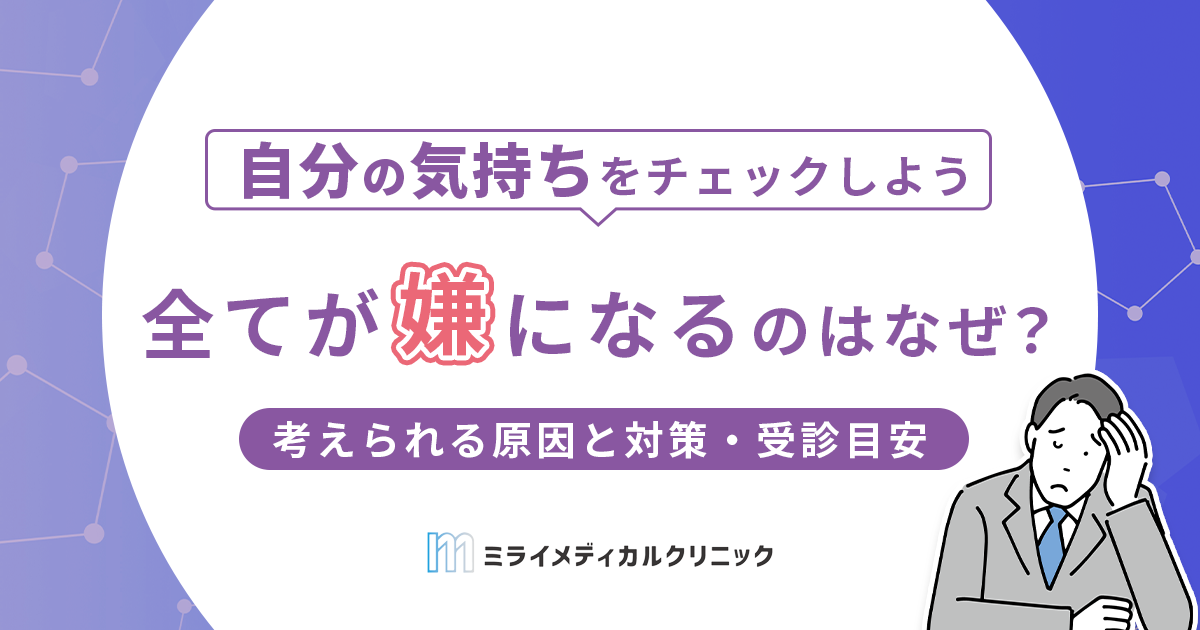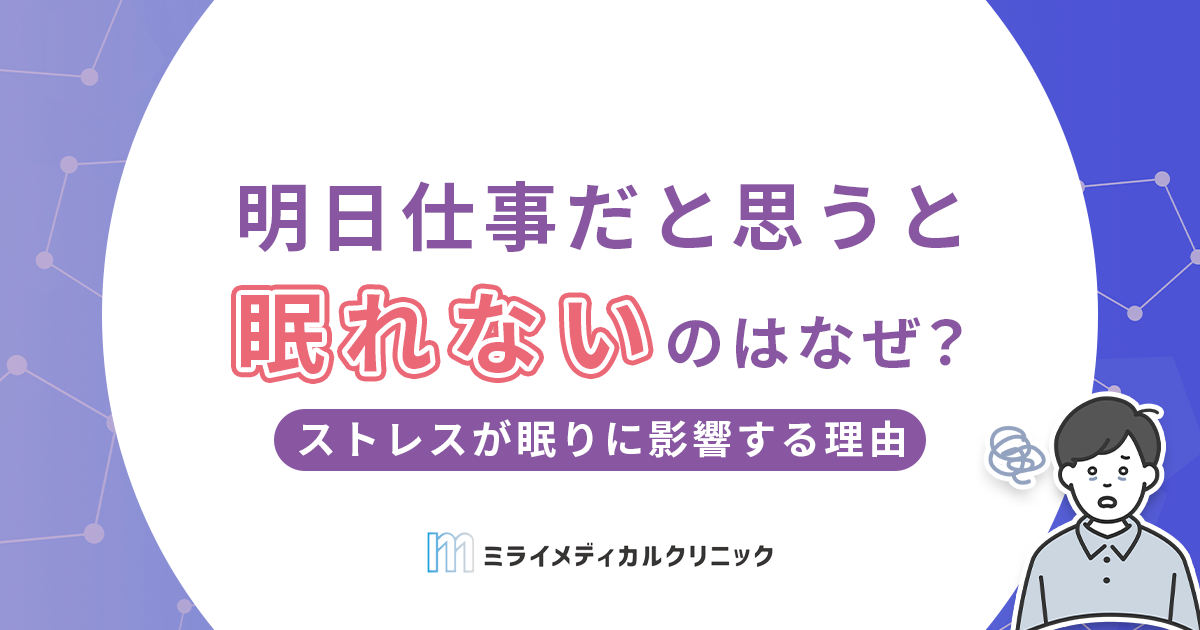急に襲ってくる不安で胸が苦しくなったり、心配事が頭から離れずに眠れなくなった経験はありませんか?「このまま気が狂ってしまうのではないか」そんな気持ちに押しつぶされそうになると、一人でどうにかしようと必死になりがちです。
不安は誰にでも起こる自然な感情です。正しい対処法で症状を軽減できます。
この記事では、不安で苦しい時に今すぐ試せる3つの方法から、専門家への相談のタイミングまで紹介します。一人で抱え込まず、できることから実践していきましょう。
目次
不安で押しつぶされそうな時にまず試してほしい3つの方法
不安に襲われた時、まずは自分でできる対処法を試してみましょう。ここでご紹介する3つの方法は、心理療法でも実際に使われている科学的根拠のある技法です。特別な道具は必要なく、どこでも実践できます。
4-7-8呼吸法で自律神経を整える

4-7-8呼吸法は、不安時に乱れがちな自律神経のバランスを整える呼吸法です。米国の医師アンドルー・ワイル博士が提唱した方法で、副交感神経が優位になりやすく、心拍数や血圧の低下が期待できます。
手順は以下のとおりです。
- 背筋を伸ばして座るか、仰向けに横になる
- 口から息を完全に吐き切る
- 口を閉じて鼻から4秒かけて息を吸う
- 7秒間息を止める
- 口から8秒かけてゆっくり息を吐く
- これを3-4回繰り返す
慣れないうちは秒数にこだわらず、4:7:8の比率を意識するだけでも効果があります。
段階的筋弛緩法で体の緊張をほぐす
段階的筋弛緩法は、筋肉の緊張と脱力を繰り返すことで深いリラックス状態を作り出す方法です。筋肉の緊張と弛緩の差を体感することで、より深いリラックスを得られます。
手順は以下のとおりです。
- 椅子に座るか床に横になる
- 両肩を耳に近づけるように5秒間力を入れる
- 一気に力を抜いて10秒間脱力する
- 両手をぎゅっと握って5秒間力を入れる
- 一気に手を開いて10秒間脱力する
- 顔の筋肉(眉間、目、口)に5秒間力を入れる
- 一気に表情を緩めて10秒間リラックス
緊張と弛緩の違いを感じ取ることで、普段無意識に入っていた力に気づけるようになります。
グラウンディング法で意識を現実に戻す
グラウンディング法は、不安で頭がいっぱいになった時に「今この瞬間」に意識を戻す技法です。5-4-3-2-1法とも呼ばれ、五感を使って現実に意識を向けます。
以下の手順で実践できます。
- 見る(5つ):周りを見回して、目に入るものを5つ声に出して言う
- 触る(4つ):手で触れるものを4つ確認し、感触を味わう
- 聞く(3つ):耳を澄まして聞こえる音を3つ確認する
- 嗅ぐ(2つ):鼻で感じる匂いを2つ確認する
- 味わう(1つ):口の中の味を1つ意識する
外出先でも自然に実践でき、周囲に気づかれることもありません。「青いペン」「木の机」「車の音」など、具体的に確認することがポイントです。
気持ちが少し落ち着いたらやっておきたいこと
不安な状態から少し回復したら、次に同じような状況になった時の備えをしておきましょう。事前の準備があることで、不安に対する心の余裕が生まれ、症状の悪化を防げます。
不安になりやすい時間や場面を把握しておく
不安には一定のパターンがあることが多いです。自分の不安の傾向を知ることで、事前に対策を講じたり、心の準備をしたりできます。
<時間のパターン>
| 時間帯 | よくある不安のタイミング | 対策例 |
|---|---|---|
| 朝 | 起床直後、出勤前 | 朝のルーティンに呼吸法を組み込む |
| 夕方〜夜 | 疲労が溜まった時 | 早めの休息、リラックスできる音楽 |
| 就寝前 | 一日の振り返り時 | 不安日記、温かい飲み物 |
| 週末 | 一人でいる時間が長い時 | 予定を作る、人と会う約束 |
<場面のパターン>
| 場面 | 具体的な状況 | 対策例 |
|---|---|---|
| 人前 | 会議、プレゼン、面接 | 事前準備、深呼吸法の練習 |
| 移動中 | 電車、エレベーター、渋滞 | 音楽、グラウンディング法 |
| 一人の時 | 自宅、休憩時間 | 信頼できる人への連絡 |
| 特定の場所 | 病院、高所、閉所 | 同伴者、段階的な慣れ |
パターンを把握できたら、該当する時間帯や場面では意識的にリラックスできる環境を整え、先ほど紹介した対処法を事前に準備しておきましょう。
信頼できる人に話を聞いてもらう
不安を感じたときは、信頼できる人に話すことが気持ちを整理するきっかけになります。一人で抱え込まず、言葉にするだけでも心の負担が軽くなり、客観的な視点を得られる場合があります。
話し相手を選ぶ際は、あなたの話を否定せずに聞いてくれる人、秘密を守ってくれる人、適切なアドバイスをくれる人(家族、友人、同僚など)を選びましょう。話すときは、不安を感じている理由や状況を率直に伝えることで、相手も状況を理解しやすくなります。
また、解決策を求めるのか、共感を求めるのかを明確にすると、相手も対応しやすくなります。話すことに抵抗がある場合は、まずはメッセージや手紙から始めてみるのも良い方法です。
不安になりにくい心身を作る生活習慣
規則正しい生活習慣は、不安を感じにくい心と体をつくる土台になります。特に、睡眠不足や運動不足は自律神経を乱し、不安を悪化させる要因になります。
急な不安に備えるだけでなく、日頃から整えた状態を保つ意識が大切です。
睡眠を整えるポイント
良質な睡眠は、脳の回復と情緒の安定に欠かせません。以下の習慣を意識することで、睡眠の質を改善しやすくなります。
- 毎日同じ時間に就寝・起床する
- 就寝1時間前はスマートフォンやパソコンを控える
- 寝室を快適な温度(18-22度)に保つ
- カフェインは就寝6時間前まで
軽い運動を習慣にする
適度な運動は、ストレス軽減や気分の安定に効果があります。激しい運動でなくても、日常の中に少しずつ取り入れるだけで十分です。
- 1日20-30分の軽い運動(散歩、ストレッチ、ヨガなど)
- エレベーターではなく階段を使う
- 一駅分歩く、早歩きを心がける
- 無理をせず、楽しめる運動を選ぶ
継続的な運動によって、気分を整える働きをもつセロトニンやエンドルフィンといった脳内物質の活性が促され、不安を感じにくい心の状態を保ちやすくなります。
不安が続く時は専門家に相談しよう
セルフケアを試しても不安が改善しない場合や、日常生活に支障をきたす場合は、専門家への相談を検討しましょう。一人で頑張りすぎず、適切なサポートを受けることで、より効果的な改善が期待できます。
受診を検討すべきサインは以下の通りです。
- 不安が2週間以上続いている
- 仕事や外出など日常生活に明らかな支障が出ている
- 動悸・息切れ・頭痛などの身体症状が頻繁に起こる
これらに当てはまる場合は、我慢せずに専門家に相談してください。
「病院に行くのは敷居が高い」と感じる方には、オンライン診療がおすすめです。自宅にいながら専門医に相談でき、症状の聞き取りから治療法の提案まで、一人ひとりに合わせたサポートが受けられます。予約から診療まで全てオンラインで完結するため、気軽に利用できます。
まとめ
不安で押しつぶされそうな時は、まず今すぐできる対処法を試してみてください。4-7-8呼吸法、段階的筋弛緩法、グラウンディング法は、特別な道具も必要なく、どこでも実践できる方法です。
気持ちが少し落ち着いたら、安心できる言葉や音楽の準備、不安のパターン把握、信頼できる人への相談など、次に備える行動を取りましょう。日常的には、規則的な睡眠と運動、不安日記の記録、意識的なリラックス時間の確保が、不安になりにくい心身の状態作りに役立ちます。
セルフケアで改善しない場合や日常生活に支障が出る場合は、遠慮なく専門家に相談してください。完璧を求めず、できることから少しずつ始めていきましょう。