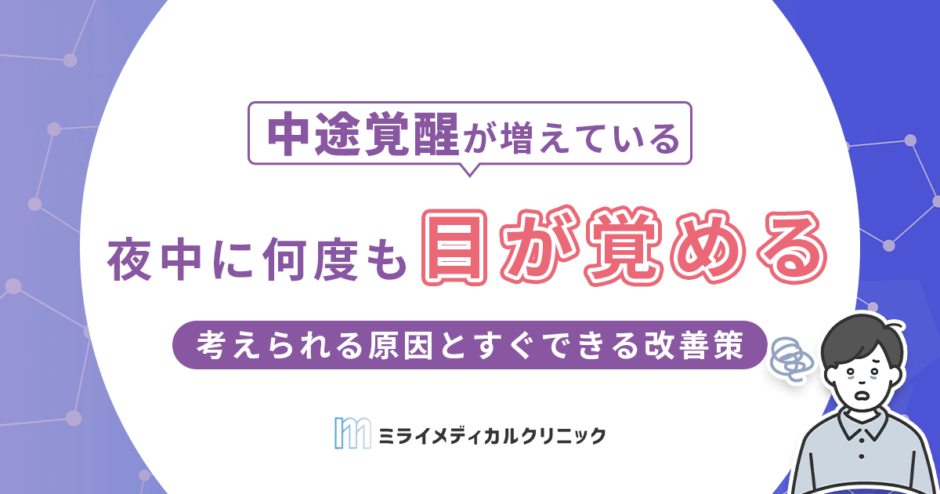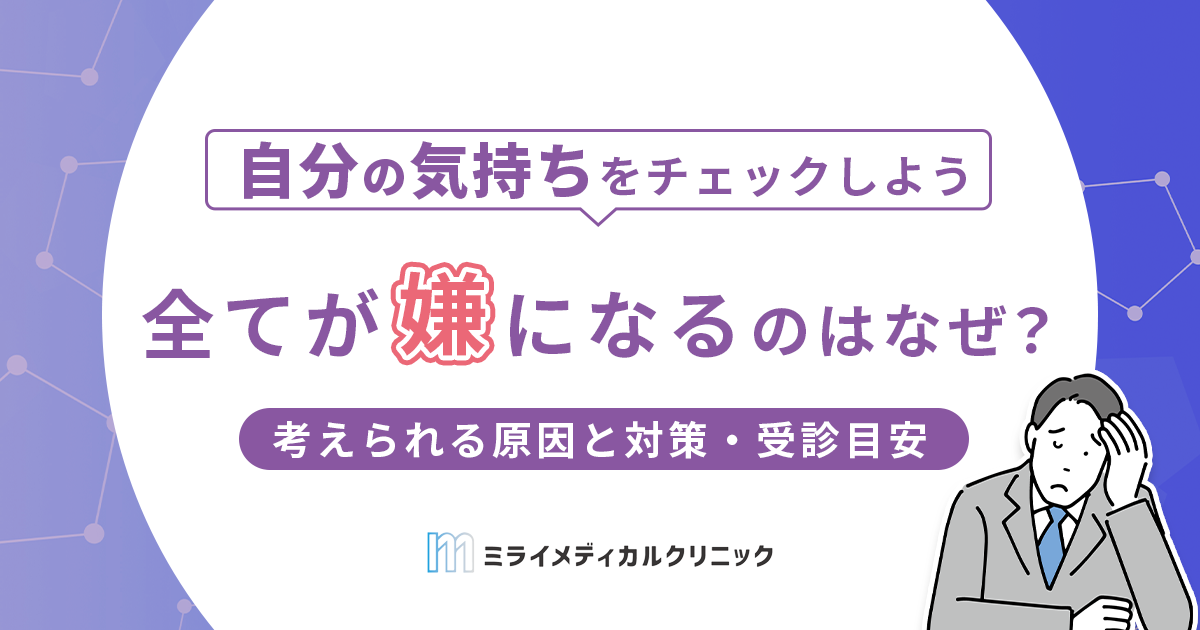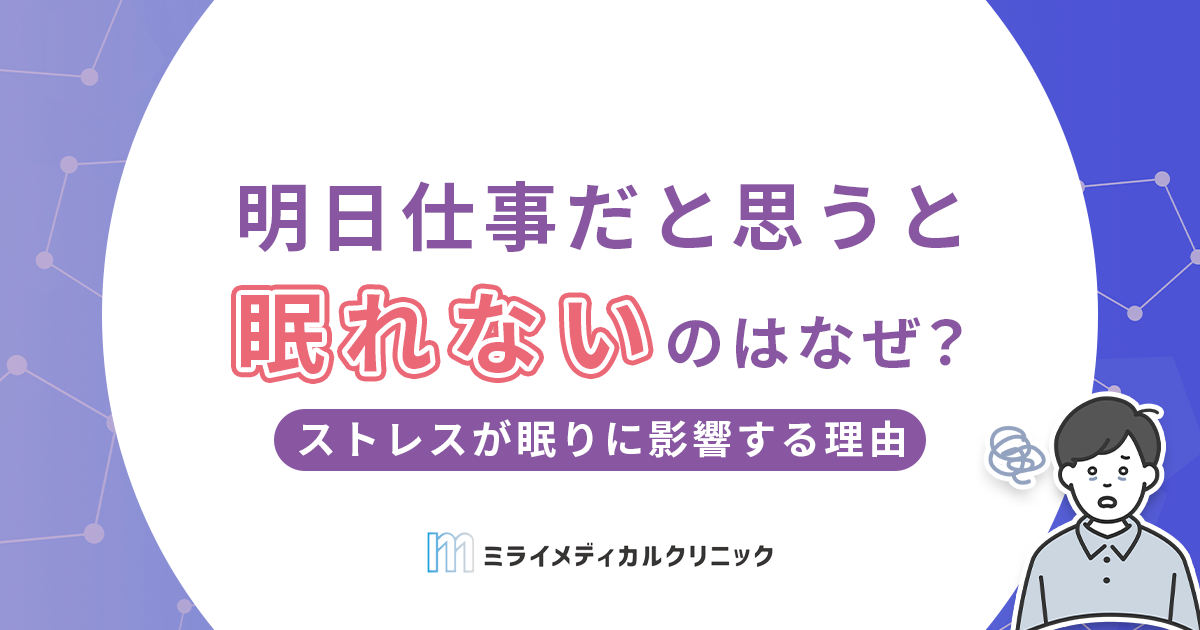夜中に何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠れた実感を持てないと感じることはありませんか。
「一度起きると眠れない」「朝までに何度も目覚めてしまう」といった症状は、中途覚醒と呼ばれる睡眠の乱れです。加齢やストレスの影響だけでなく、睡眠の質や体調の不調が関係しているケースも見られます。原因がはっきりしないまま、漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、夜中に目が覚める原因や背景を整理したうえで、再び眠りにつきやすくなるための対処法や、生活習慣を整えるためのポイントを解説します。改善のきっかけを探している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
夜中に何度も目が覚める…よくある原因とは
夜中に目が覚めることは、誰にでも一度は起こる自然な現象です。しかし、それが頻繁に繰り返される場合は、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。
ここでは、よく見られる3つの主な原因を紹介します。
加齢や体内リズムの変化によるもの
年齢を重ねると、深い睡眠(ノンレム睡眠)の割合が大幅に減少し、睡眠が浅くなりやすくなります。研究によると、深い睡眠の割合は年齢に伴って減少し、中年期以降では若年期と比べて半分以下になることが報告されています。深い睡眠が減ることで、少しの物音や体の不快感でも目が覚めやすくなるでしょう。
また、加齢によって体内時計(概日リズム)の働きが変化し、夜間に分泌されるはずの睡眠ホルモン(メラトニン)が減少することも、中途覚醒の一因とされています。
参考:正常睡眠における脳波パターン(メドスケープ医学事典)・正常な加齢における睡眠変化(米国国立医学図書館)
ストレスや緊張で眠りが浅くなる理由
日中の緊張や心配ごとを抱えて眠ると、脳が完全に休息モードへ移行できません。特にストレスが続いていると、交感神経が優位な状態が夜間まで持ち越され、睡眠が浅くなりやすいです。
通常、健康な睡眠では副交感神経が優位となり、心拍数や血圧が低下して深い眠りが得られます。しかし、ストレス状態では交感神経の活動が続くため、心拍数の上昇や筋肉の緊張が維持され、浅い睡眠となってしまいます。
こうした状態では小さな刺激で目が覚めやすくなるうえに、覚醒後も交感神経の興奮が残っているため気持ちが落ち着かず、再び眠りにつくのが困難になるでしょう。
睡眠時無呼吸や頻尿など病気が関係する場合も
夜間の目覚めが続く背景には、病気が隠れている場合もあります。以下のような症状がある方は注意が必要です。
- 睡眠中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある
- 何度もトイレに起きる(夜間頻尿)
- 動悸や発汗で目が覚める
- 気分の落ち込みや強い不安が続いている
これらの症状は、睡眠時無呼吸症候群、前立腺肥大・過活動膀胱、不安障害やうつ病などの可能性があります。頻度が高い場合や日常生活に支障が出ている場合は、医療機関での相談を検討してください。
目が覚めたあとにすぐ眠れないときの対処法
夜中に目が覚めたあと、布団の中でなかなか眠れず、時間だけが過ぎてしまうこともあるでしょう。こうした状態が続くと、「また今日も眠れないのでは」と不安が募り、かえって眠れなくなる悪循環に陥りやすくなります。
ここでは、再入眠を妨げる行動や、眠りやすくするための工夫について解説します。
やってはいけないNG行動と正しい対処法
目が覚めた直後、無意識にとっている行動が再入眠を妨げている場合があります。次のような行動には注意が必要です。再入眠を妨げるNG行動の例は以下のとおりです。
- スマートフォンやテレビを見る
- 時計を確認して時間を気にする
- 寝返りを繰り返す・ため息をつく
- 「早く寝なきゃ」と焦ってしまう
これらの行動は、脳を再び覚醒させてしまう要因になります。とくにスマホの光やSNSなどの刺激は、眠気を遠ざけてしまいます。
対処法としては、焦らず一度目が覚めるのは自然な現象だと受け止める姿勢が重要です。布団の中でじっとしているのがつらいときは、部屋の照明を落としたまま静かに椅子に座る、軽くストレッチをするなどの方法も有効です。
再入眠を助ける行動と考え方のコツ
再び眠るためには、心と体の緊張をやわらげ、自然と眠気が戻ってくる状態をつくりましょう。以下のような工夫を試してみてください。
再入眠を助ける行動の例は以下のとおりです。
- ゆっくりと腹式呼吸を行う
- 軽く手足を伸ばしてストレッチをする
- 温かい飲み物(白湯など)を少量飲む
- 眠気が戻るまで静かに読書する(紙の本)
また、早く寝なければと思うほどプレッシャーがかかり、かえって眠れなくなりがちです。再入眠できなかったとしても、体を横にして目を閉じているだけでも十分な休息になります。眠れなくてもいいと気持ちを緩めれば、結果的に眠りを促す助けになるでしょう。
20〜40代にも増えている中途覚醒の背景
中途覚醒は年齢を重ねるほど起こりやすいとされますが、最近では20〜40代の比較的若い世代でも、同じような睡眠の悩みを訴えるケースが増えています。
ここでは、若い世代で中途覚醒が起こる背景と、現代的な生活習慣との関係について見ていきましょう。
若い世代の中途覚醒が増えている理由
本来、中途覚醒は加齢にともなう睡眠構造の変化が原因とされてきました。しかし近年では、20〜30代でも「夜中に目が覚めてしまう」「途中で眠れなくなる」といった相談が増えています。
背景には、生活の不規則化や慢性的な疲労、精神的ストレスの蓄積などが関係しているでしょう。仕事や子育てなどによる多忙さに加え、夜遅くまでの作業や情報への接触機会が多いなどが睡眠に影響を及ぼす要因となっていると考えられます。
厚生労働省「国民健康・栄養調査」では、20〜50歳代で「日中、眠気を感じる」人の割合が高いと報告されています。同調査からは、睡眠の質の低下が若い世代でも課題となっており、従来は高齢者特有とされていた睡眠の悩みが、若い世代にも広がっているのではないでしょうか。
スマホやSNSが眠りに及ぼす影響
夜遅くまでスマホやパソコンの画面を見ていると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、脳が覚醒状態のまま入眠してしまいます。
また、SNSや動画コンテンツによる感情の刺激や情報処理が続くため、睡眠の質そのものが低下しやすくなります。
スマホ利用による睡眠への影響は以下のとおりです。
- メラトニンの分泌を妨げるブルーライトの影響
- SNSや動画による感情の刺激
- 入眠直前までの使用で睡眠リズムが乱れる
中途覚醒が気になる場合は、就寝前1時間はスマホを見ない、照明を落とすなど、脳を休息モードに切り替える習慣づけが効果的です。
自己対処が難しいときは医療の力も検討しよう
生活習慣を見直しても中途覚醒が続く場合は、医療機関への相談も選択肢のひとつです。
週に3回以上目が覚める、日中の眠気や集中力低下が続く、息苦しさや不安感を伴うといった症状がある場合は、睡眠障害が疑われます。状態が長引く場合は、早めの受診をおすすめします。
通院が難しい方には、オンライン診療という方法もあります。自宅から医師に相談できるため、忙しい方でも無理なく利用できます。
受診の際は、就寝時間や目覚めた回数、日中の体調を簡単に記録しておくと、診療がスムーズに進みやすくなります。
まとめ
夜中に何度も目が覚める中途覚醒は、誰にでも起こり得る身近な睡眠の乱れです。
加齢やストレス、生活習慣などさまざまな要因が関係しており、再入眠の工夫や日中の過ごし方によって、改善が期待できるケースも少なくありません。
生活習慣を見直しても変化がない場合は、無理をせず、医療機関やオンライン診療を頼ることも一つの方法です。
できることから少しずつ始めて、安心して眠れる夜を取り戻していきましょう。